(関連目次)→勤務医なんてやってられない!
(投稿:by 僻地の産科医)
 日経メディカル6月号から!!
日経メディカル6月号から!!
いつもの「医療訴訟のそこが知りたい」のシリーズです(>▽<) ..。*♡
勤務医の過失で患者死亡
病院より医師の責任重く
蒔田 覚 仁邦法律事務所
勤務医の過失で死亡した患者の遺族に示談金を払った病院が、勤務医を被保険者とする医融資保険による全額保証を求めました。保険会社は医師の責任割合を示談金の5割未満としましたが、裁判所はより高く判断しました。
(Nikkei Medical 2008.6 p156-158)
まきたさとる氏
弁護士。裁判所書記官を経て、1996年司法試験合格。2001年仁邦法律事務所に入所。医療者側の弁護士として、医療訴訟を専門に弁護活動を行う。
事件の概要
患者Aは2003年11月29日、B病院にて変形性脊髄症と診断され、傍胸部神経ブロックなどの治療を受けることとなった。同年12月9日午後3時ころ、B病院に勤務するC医師が、脊部の疼痛を緩和するため星状神経節ブロック(SGB)を施行。SGBは約1分で終了し、30分ほど安静にした後、患者Aは帰宅した。
ところが、Aは同日午後4時過ぎに口唇チアノーゼ、呼吸困難などの症状を起こし、救急車で近くの県立病院に搬送された。搬道中に呼吸、心停止に陥り、県立病院に入院後、一度は自発呼吸を回復したが、治療のかいなく、12月17日に死亡した。
その後、05年7月5日、SGBを施行したC医師と雇用主であるB病院とが連帯で、患者Aの遺族らに3000万円を支払う示談が成立。B病院は7月26日に、C医師の賠償分も含めて3000万円全額を支払った。
一方、B病院の経営者は、C医師を被保険者とし、1医療事故当たりの保険金の限度額を5000万円とするD損害保険会社の医師賠償責任保険に加入していた。このため、B病院の経営者は、D損害保険会社からC医師に支給される保険金の請求権をC医師から譲り受け、D損害保険会社に示談金と同額の3000万円の保険金の支払いを要求した。
ところが、D損害保険会社は、3割に相当する900万円しか支払わない旨を回答。これを不服としたB病院は、D損害保険会社に3000万円の支払いを求めて提訴した。
裁判では、D損害保険会社は「B病院のC医師に対する求償の範囲(B病院が支払った示談金3000万円のうち、C医師が賠償責任に応じて負担すべき額)は信義則上、示談金全額の5割を超えることはない」と主張して、求償の範囲を争った。
判 決
裁判所はまず、医療過誤の内容について、
①専ら医師の手技上の過誤によるものである
②SGBが困難かつ侵襲の高い医療行為とはいえない――と判じた。
その上で、
③勤務医の勤務条件が過酷な状態にあったとは認められないこと
④医療行為が医師の裁量に委ねられていること
⑤今回の医療過誤が院内の物的設備や人的態勢などの不備や不具合により発生したものではないこと
⑥医師が専門性に見合った高額な報酬を受けていたこと
⑦B病院が保険料を負担して、C医師を被保険者とする損害保険に加入するなど、損害を回避する措置を講じていたこと
―――を挙げ、C医師の雇用主であるB病院の普段の雇用状況に問題がなかったと判断。これらから、B病院がC医師に対して求償権を行使することは信義則に反しないとした。
さらに、C医師とB病院の賠償の公平な負担の観点から、B病院のC医師に対する求償権は制限されるべきであるとしたD損害保険会社の主張に対しては、
①今回の事故が通常の診療時間・業務の過程で発生したこと
②専ら(医師の過誤により起こったこと
③C医師は適正な給与・労働条件の下、雇用されていたこと
――などから、B病院の求債権は制限されないと判示。結果、B病院の主張を全面的に認め、D損害保険会社に3000万円および年6%の遅延損害金の支払いを命じた(盛岡地裁07年6月5日判決)。
解 説
民法709条は、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています,今回のケースにおいて医療ミスをした医師は、同条により患者に対して損害賠償責任を負うことになります。
一方、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第3者に加えた損害を賠償する責任を負う」とした民法715条により、医師の雇用主である病院も使用者責任を負担しています。これは、使用者の病院に賠償責任を課すことで、より手厚い被害者救済を図れるようにしたものです。
本件では、C医師の使用者であるB病院が患者への示談金を全額負担した後で、C医師の賠償責任をかんがみて、B病院のC医師に対する求償がどこまで認められるかが問題となりました。使用者責任はかつて、被害者保護のために究極的責任(第1次的責任)を負担する被用者(本件の場合はC医師)に代わって、その使用者に賠償義務を課すものと考えられていたので、使用者が被害者に払った全額を被用者に請求できるという理解がなされていました。
それが今日では、「使用者は危険性のある業務に被用者を従事させ利益を得ているにもかかわらず、企業活動から生じる損害をすべて被用者に負担させるのは不当である」との考え方が一般的になっています。タンクローリーの運転手が業務中に交通事故を起こした事案について、信義則上、求償権が制限されるという判断(最高裁1976年7月8日判決)が示されて以降、裁判実務においては、被用者に対する使用者の求償を制限する運用が定着しています。D損害保険会社の主張は、こうした判例を背景としたものです。
これに対して本件では、信義則上、求償が制限される場合があることを認めつつ、「判決」で挙げた①~⑦および①~③のように詳細な検討を行い、こうした具体的な事情の下では求償は制限されないと判示しました。この判決には、B病院が支払いを求めた相手がC医師ではなく、損害保険会社であったことが影響した可能性も否定できません。
医師は国家資格を持つ専門家として確固たる地位にあること、診療において広範な裁量が認められていること、高額な報酬を受けていること――を勘案すると、仮に求償が制限されるとしても、その程度は他職種ほど高くないと考えられます。このため、仮に医賠貴保険に加入していないとしても、医師は高額な賠償金を求償される可能性があります。
近年、2億円を超える賠償を認めた事例が散見されるなど、医療訴訟の賠償は高額化しています。また、保険金支払いの免責範囲を広げる保険会社も出始めており、病院の加入する賠償保険で全損害をカバーできない例が増えることも危惧されます。このため、病院が賠償保険に加入しているからといって安心はできません。医師個人でも積極的に賠償保険に入ることが望まれます。
最後に、本件における患者Aの死因について触れておきます。
死因は「血腫による気道閉塞」とされていますが、血管損傷、血腫発生(血腫による気道狭窄、気道閉塞)はSGBに伴う合併症の一つです。なお、同施術後30分の経過観察において異常が確認されていません。
判決では、「血管を避けて針を剌すべきところ、誤って刺してしまった」ことをもって医師の過失ととらえています。しかし、SGBは血管の走行を直視しながら行う施術ではないので、誤って剌した事実だけで過失といえるかは微妙な部分もあります。
本件の争点は、D損害保険会社に対する保険請求に関するものであったため、C医師の具体的な手技内容についての詳細な検討はなされませんでした。従って、この裁判例は、SGBの過失評価について先例的価値を有するものではありません。
3分でわかる 判決のポイント
裁判例では、最終的に保険会社が示談金を負担しましたが、保険を全く掛けていなければ、医師が病院から直接求償される可能性はあるのでしょうか?
今回の裁判は、病院と保険会社との間の求償関係について判断したものです。しかし、不法行為の究極的責任(第1次的責任)は医師にありますので、医師個人に対して病院が求償することは可能です。
具体的な求償の範囲は、本例で盛岡地裁が示したような基準を参考にしながら、個別事案ごとに検討されることになります。医師の賠償保険加入の有無は、病院と医師との負担割合を検討する際の一要素となりますが、タンクローリーの運転手についての最高裁の判例とは異なり、医師としての業務の性格上、求償権行使の大幅な制限が認められる余地は少ないと考えられます。
また、今回の事例は医師の不法行為責任としての賠償に関するものですが、病院が患者との契約責任(債務不履行責任)として賠償金を払った場合も、同様の基準で負担割合が決定されます。
医療ミスをした医師が病院から求償された場合、賠償金の全額を支払うこともあるのでしょうか?
病院の医師に対する求償の範囲は事案によって異なり、医師個人が賠償金の全額を負担しなければならないことはあリ得ます。
ただ、例えば外科的手術の場合、
①侵襲の高い医療行為であること
②チーム医療としての側面が強いこと
③物的設備や人的態勢などの不備、不具合が介在する余地の大きいこと
などがら、信義則上、病院から医師個人に対する求償権は制限される余地があります。
また、医師の勤務形態が過酷な中での事故の場合(36時間連続勤務など)には、使用者である病院の求債権の行使が大幅に制限されることも考えられます。


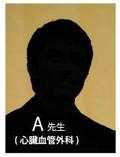
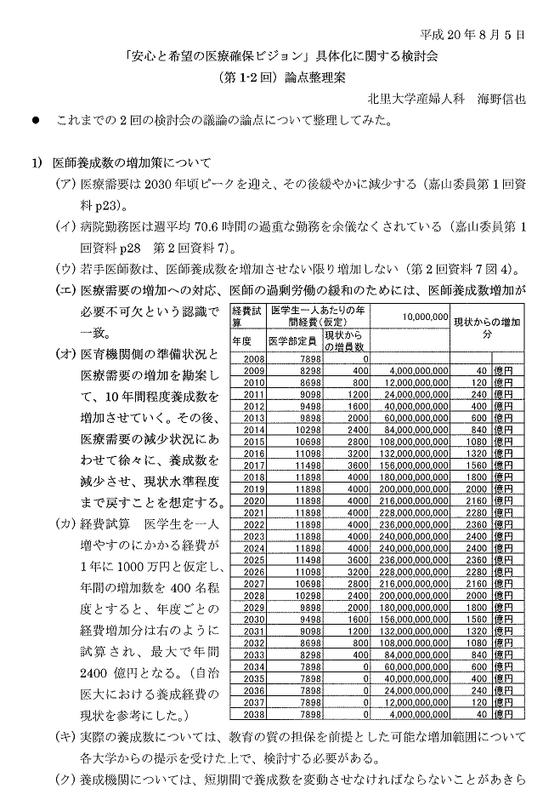
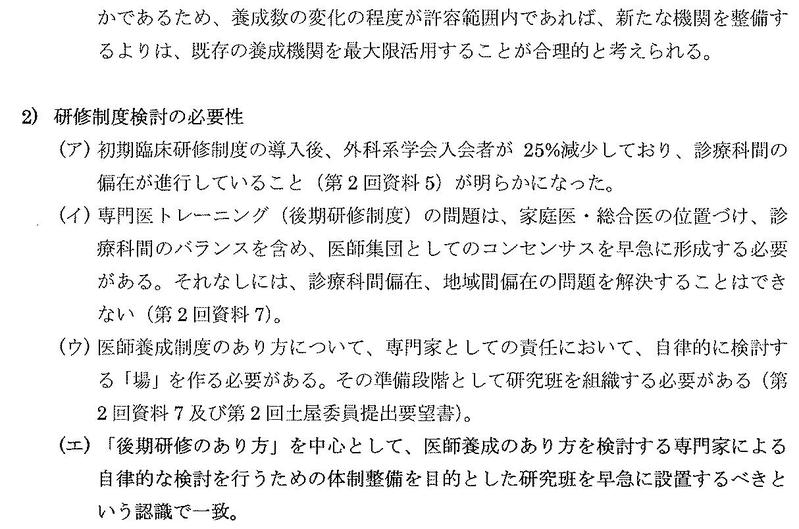
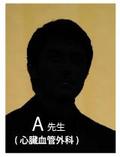


最近のコメント