(関連目次)→大淀事件
ぽち→ 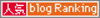
(投稿:by 僻地の産科医)
大淀事件 判決文が裁判所から公開されました!
妊婦が分娩中に脳出血を発症して死亡したことにつき,被告病院医師がCT検査等を実施しなかった点に過失はなく,死亡との因果関係も認められないとして,損害賠償請求が棄却された事例(大淀病院事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38718&hanreiKbn=03
全文はこちら
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100318100440.pdf
1 主文
1 原告らの各請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告A(以下「原告A」という。)に対し,連帯して4728万3748円及びこれに対する平成18年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告B(以下「原告B」という。)に対し,連帯して4078万3748円及びこれに対する平成18年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,C(以下「C」という。)が分娩のため大淀町立大淀病院(以下「被告病院」という。)に入院中,脳内出血が生じたところ,被告病院産婦人科の被告D医師(以下「被告D医師」という。)が,子癇であると誤診して頭部CT検査を実施せず,速やかに高次医療機関へ転送すべき義務を怠った結果,Cが脳内出血により死亡したと主張して,Cの夫である原告Aが,被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,損害賠償金4728万3748円及びこれに対する平成18年8月8日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,Cの子である原告Bが,被告らに対し,同様に,4078万3748円及び上記起算日・割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。(なお,以下,日付のみ又は時刻のみを記載したものは,直前と同一の月又は日を示す。)
1 前提事実
(争いがない事実及び括弧内に掲記の証拠により容易に認定できる事実)
(1) 当事者
ア C(昭和49年6月1日生)は,平成17年5月5日に原告Aと婚姻し,平成18月8月7日,分娩のため奈良県吉野郡大淀町所在の被告病院に入院し,8日午前5時47分ころ大阪府吹田市所在の国立循環器病センターへ転送され,16日,同所にて死亡した。
原告Bは,原告AとCの子として,8日,国立循環器病センターにおいて,41週と2日,体重2612gで出生した。
イ 被告大淀町は,被告病院を開設・運営している。
被告D医師は,平成18月8月当時,被告病院産婦人科に勤務していた。
(2) 診療経緯(甲A1~6,乙A1~11)
ア Cは,平成17年12月20日以降,定期的に被告病院産婦人科医師の診察を受け,分娩予定日は平成18年7月30日であった。
イ Cは,8月7日午前9時20分ころ,分娩目的で被告病院に入院した。
ウ Cは,8日午前零時ころ,頭痛があり,こめかみが痛いと訴えた。この時点でのCの血圧は,収縮期圧が155mmHg,拡張期圧が84mmHg(以下,収縮期圧及び拡張期圧を「155/84」などと記載し,単位を省略する。)であった。
Cは,午前零時14分ころ,意識を消失した。被告D医師がCを診察したところ,血圧(147/73),呼吸に問題はなく,SpO2(血中酸素飽和度)は97%であった。被告D医師は,同日被告病院に当直していた内科のE医師(以下「E医師」という。)にCの診察を依頼したところ,E医師は,Cの瞳孔は丸くて左右差がなく,胸部に異常もなかったため,Cを失神していると診断し,経過観察を助言した。その後,F助産師(以下「F助産師」という。)が,午前零時30分ころから午前1時37分ころまでの間,Cの血圧の測定,分娩監視装置の装着等を行っていた。Cは,午前1時37分ころ,血圧が上昇し(自動血圧計175/89,水銀血圧計200/100 ),けいれん発作がみられた。被告D医師は,Cに対するマグネゾール(一般名・硫酸マグネシウム)の静脈注射を指示した。
被告D医師は,午前1時50分ころ,奈良県立医科大学附属病院(以下「奈良県立医大」という。)に対し,電話で母体搬送を依頼した。被告病院では,午前3時49分,中吉野広域消防組合消防本部に対し救急車の出動を要請し,救急車は午前3時56分に被告病院に到着し,待機していた。
Cは,午前4時30分ころ,呼吸困難となったため,E医師が気管内挿管を実施した。
エ Cは,午前4時49分,国立循環器病センターへの搬送が開始され,午前5時47分に到着した。搬送時のCの状態は,呼吸20回/分,血圧163/99,脈拍123回/分,意識状態JCS(ジャパンコーマスケール)300であり,瞳孔が中等度散瞳して固定しており,両側の瞳孔が5㎜で対光反射はなかったが,自発呼吸は残存していた。国立循環器病センターにおいて午前6時20分ころ実施された頭部CT検査によると,右前頭葉に径7cmの血腫が認められ,著明な正中偏位があり,脳幹部にも出血が認められ,脳室穿破を伴うと診断された。そこで,午前7時55分ころ,Cに対する開頭血腫除去術及び帝王切開術が開始された。午前8時4分,原告Bが出生し,Cは,右被殻出血が認められ,一部が視床に及んでおり,その後血腫が除去され,午前10時ころ手術が終了した。
オ Cは,16日,死亡した。死因は脳内出血であった。
2 争点及び争点に対する当事者の主張
(1) Cの診療経過
(原告らの主張)
ア Cの死因は,右前頭葉に発生した脳出血による脳ヘルニアであり,右前頭葉の出血は,8日午前零時ころ発生した。
午前零時ころ以前はCに高血圧所見がなかったところ,同時刻ころ血圧が155/84に上昇し,その後転送が開始された午前4時49分までの間高血圧が持続したことからすれば,午前零時ころ脳出血が始まり,以降高血圧性の出血が持続したといえる。
国立循環器病センターにおいて,右被殻出血があると診断され,また,出血の一部が視床に及んでいたことからすれば,8日午前零時ころの出血の発生部位は右被殻部であり(高血圧性脳出血の好発部位は被殻であること,Cが右こめかみ痛を訴えていたこととも合致する。),その後の6時間で出血が進行して被殻部の血腫が拡大し,その一部が視床下部に及んで脳幹を圧迫したと考えられる。
すなわち,Cは,午前零時ころに脳出血が発生し,午前零時10分ころは応答開眼していたが(JSC20),午前零時14分ころに突然意識を消失して応答しなくなり,午前1時ころからは徐々に痛覚刺激を与えなければ反応しなくなり(JSC100~200),午前2時ころには疼痛刺激に対して拳を握って両上肢を伸ばして内側に曲げ,両下肢を突っ張るという除脳硬直姿勢を呈し,対光反射があり,瞳孔はやや開き気味であり,午前3時ないし4時の時点では,痛み刺激に対する反応があり(JSC200),瞳孔4~5㎜で中等度固定,呼吸正常であり,午前4時49分の国立循環器病センターへの転送後は昏睡(JCS300)となっていることからすれば,脳組織の損傷は約6時間かけて徐々に進行したと考えられる。
以上からすれば,Cは,午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば,十分に救命できたと考えられる。
イ 8日午前1時37分ころにF助産師が発見したとされるけいれん様発作は,脳出血に起因する除脳硬直によるものである。
原告Aは,午前1時37分ころ,突然Cの両上肢が硬直し,拳を強く握って腕を内側に曲げ,つま先が突っ張った姿勢をとっているのを観察し,F助産師にその旨告げた。また,脳外科病棟の看護師としての経験が長かった原告Aの祖母が,午前2時ころCを観察して除脳硬直であり脳内病変が疑われるので頭部CT検査などの検査を実施するよう被告D医師に対して再三にわたって依頼している。
被告らは,上記けいれん様発作が子癇によるものであると主張するが,子癇は妊娠高血圧症候群に罹患している場合の症状であるところ,Cには午前零時に脳出血が発症する以前には高血圧所見が認められていないこと,子癇は可逆的な病態であり血管性脳浮腫による刺激が原因であるからけいれん発作の持続期間は数十秒ないし1,2分であり,長時間意識消失が続くことはないことから,上記けいれん様発作が子癇によるものであるとは考えられない。
(被告らの主張)
ア Cの死因は脳出血であり,右前頭葉の巨大血腫がもたらした脳ヘルニアの関与が顕著であるが,国立循環器病センターで同時に認められた発症時期・機序が不明の脳幹出血が上記巨大血腫とは別にCの死亡に関与した可能性も否定できない。脳幹出血には,ヘルニアで併発するデュレ出血以外に,自然出血も報告されており,独立した脳出血として扱われている。上記血腫をもたらした右前頭葉の出血は8日午前4時前後に始まり,極めて短時間で脳幹部を圧迫するほどの大出血となり,国立循環器病センターで頭部CT検査が実施された午前6時20分ころまでに脳ヘルニアが完成した。Cに午前4時前後になって初めてクッシング現象(頭蓋内圧亢進に対抗して血圧を脳に送り出すため心臓が強くゆっくり拍動する結果,収縮期圧が上昇して拡張期圧が下降し,心拍数が低下すること)がみられ,呼吸障害や体温上昇(呼吸中枢のある延髄や体温中枢である視床下部に障害が及んだ結果であると考えられる。)もほぼ同時期にみられていることからすれば,この時点で右前頭葉の出血が始まり,午前6時20分ころまでの間に脳ヘルニアが完成したと考えられる。
原告らは,まず右被殻部に出血が生じ,それが進行してテント上ヘルニアが進行したと主張するが,どの部位の出血がどのような順序で発生したかは,頭部CT検査からは明らかにならず,臨床症状から推測せざるを得ないところ,原告らが主張するとおりの経過であれば,まず鈎ヘルニアが発生して病巣側の瞳孔不同や共同偏視が生じ,その後皮質硬直を経て除脳硬直が発生するのが通常の経過であるところ,Cはこのような経過をたどっていない。
もっとも,被告らにおいても,鑑定人らの意見を尊重し,午前零時ころに脳出血が発生したことを否定するものではない。
イ 8日午前午前1時37分ころに発生したCのけいれんは子癇によるものであり,午前零時から1時37分ころのけいれんに至る経過は,子癇の症状(意識消失に始まり,瞳孔散大,眼球上転等から全身の強直性けいれんを経て間代性けいれんに移行する。呼吸停止を伴い顔面チアノーゼとなるが,1,2分でけいれんは弱まり,昏睡に陥る。軽症では次第に意識が回復するが,重症では昏睡のまま発作が反復し,死に至ることがある。)及びその前駆症状(頭痛,眩暈など脳症状,眼華閃発,羞明,視力障害等の眼症状,胃痛,吐気,嘔気等の消化器症状)とほぼ合致する。マグネゾールの投与によってCのけいれんが消失したことからも,上記けいれんが子癇によるものであることが裏付けられる。子癇は軽度の妊娠高血圧症候群でも,正常群でも発症し得,子癇によって致死的な脳出血が生じることもあり得る。
原告らは,Cの午前1時37分ころのけいれんが除脳硬直によるものであると主張するが,除脳硬直とは,延髄よりも中枢側の中脳・橋の損傷による症状で,脳ヘルニアの発生により障害が脳幹部に及び,大脳から脊髄までの神経経路が脳幹レベルで遮断されることによって生じる症状であり,上記けいれんが除脳硬直によるものであったとすれば,この時点で既にテント上ヘルニアが不可逆的な状態に陥っており,頭蓋内圧亢進症状が発症しているはずであるところ,前記のとおりCに頭蓋内圧亢進症状が発症したのは午前4時ころであることからすれば,Cの上記けいれんが除脳硬直であったということはできない。さらに,脳出血の初期症状は通常出血部位による局所症状や片麻痺であり,突然の意識消失やけいれんは生じない。
(2) 頭部CT検査を実施せず,転送が遅延した過失
(原告らの主張)
ア Cは,8日午前零時ころ頭痛があり,こめかみが痛いと訴え,大量の嘔吐があり,血圧が上昇しており,午前零時14分ころ意識を消失し,数分経過しても意識が回復せず,高血圧が持続していたのであるから,被告D医師は,午前零時14分ころから数分間経過した時点でCの意識の消失が一過性のものではないと判断し,脳内病変を疑って頭部CT検査など(その結果次第で更に脳病変の有無を確認する必要がある。)を実施し,高血圧脳症あるいは脳出血と診断した上で脳出血の診察ができる高次医療機関へ転送すべきであった。
また,Cが8日午前零時14分ころに意識を消失してから数分経過した時点で頭部CT検査を実施していれば,午前1時までには脳出血の存在が明らかになっていた。この場合,脳圧降下剤等の早期投与を受けるとともに,脳外科救急機関は数多くある(交通事故等の外傷救急機関であれば対応可能である。)ことから,搬送先を確保することは困難でなく,より早に治療を受けることができた。
イ 被告らは,Cを子癇と診断したことは適切であったと主張するが,子癇であるとの診断は,脳内出血など(てんかん,2次性けいれん)を除外できた場合に初めて可能となり,鑑別のためには頭部CT検査又は頭部MRI検査を実施する必要がある。また,Cに妊娠高血圧症候群の症状はなく,被告D医師もCを妊娠高血圧症候群と診断していない。
さらに,脳内出血は緊急手術を要すること,子癇は脳内出血との鑑別が必要であること,被告らも当時被告病院において頭部CT検査を実施することが可能だったことを認めていることからすれば,突然の高血圧,激しい頭痛,嘔吐,意識障害といった症状があったCに対し,被告D医師には頭部CT検査を実施すべき義務があり,被告D医師が子癇を疑っていたことをもってその義務を免れることはできない。
(被告らの主張)
ア 8日午前零時ころから午前1時37分ころまでの被告D医師の措置についてみると,Cが午前零時14分ころに意識を消失した後,被告D医師は当直していた内科のE医師に診察を依頼し,瞳孔は丸く変化がなく,胸部に異常がなく,けいれんがないと診断されたため,経過観察とし,F助産師が,午前零時30分ころから午前1時37分ころまでの間,約10分に1回の間隔で訪室してCの血圧を測定し,分娩監視装置の装着などを行っており,これらの措置は適切であった。また,この時点でCに対し頭部CT検査を実施すべき義務はなかった。
午前1時37分ころ以降の被告D医師の措置についてみると,前記のとおり,Cの午前1時37分のけいれんは子癇であったのであるから,けいれん発生後,マグネゾールの静脈注射を指示した上で安静にさせ,経過観察を行った被告D医師の措置は適切であり,この時点で頭部CT検査を実施すべき義務はなかった。
また,子癇であるとすれば帝王切開術が必要となる事態が予測されるところ,被告D医師は,子癇の状態が続いた場合全身麻酔が必要となること,産科医が被告D医師だけでは対応できないことから,速やかに転送すべきと判断して上記けいれん発生後直ちに奈良県立医大の母体搬送システムに搬送先を探すように依頼しており,この措置は適切であった。また,頭部CT検査によって脳出血と確定した上で転送すべきであったとはいえない。
イ 仮に,原告らが主張するように,Cに8日午前零時ころ脳出血が発生しており,午前零時14分ころの意識消失が脳出血によるものであったとしても,子癇と脳血管障害との鑑別は困難であり,子癇である場合が圧倒的に多いこと,本件において実際にマグネゾールの静脈注射によってけいれんが治まったことからすれば,被告D医師が脳出血の可能性が否定されていなくても子癇発作であると判断してその治療を優先させて上記措置を行ったことは適切であり,安静を優先させて頭部CT検査を実施しなかったことも適切であった。
なお,疫学的研究結果として,分娩前後の頭痛,血圧上昇,意識喪失,嘔吐などの症状がみられた場合,他原因が明らかになるか,又は,局所の脳神経異常症状,持続する昏睡が認められる場合やマグネゾールの投与が奏効しない場合を除いて,妊娠高血圧症候群や子癇と考えて子癇の治療をすべきであり,現状では子癇以外の脳血管障害の診断の遅れや誤診は回避しがたいとされている。
(3)因果関係
(原告らの主張)
Cが8日午前零時14分ころに意識を消失してから数分経過した時点で頭部CT検査を実施していれば,午前1時までには脳出血の存在が明らかになっていた。この場合,脳圧降下剤等の早期投与を受けるとともに,脳外科救急機関は数多くあることから,搬送先を確保することは困難でなく,搬送先で速やかに血腫除去術が行われていれば,Cが一命をとりとめた高度の蓋然性がある。すなわち,Cにおいて8日午前零時ころ発生した脳出血は被殻出血であり,一般に被殻出血の外科療法による死亡率は約22%にとどまり,被殻出血による血腫が少量にとどまっている場合は組織への影響は軽度で良好な予後が期待できるところ,前記のとおり,Cは,午前3時ないし4時の時点では,痛み刺激に対する反応があり,JSC200,瞳孔4~5㎜で中等度固定,呼吸正常であり,午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば,十分に救命できたと考えられる(国立循環器病センター到着時の午前6時30分ころの時点でも,瞳孔は5㎜であり,散大固定には至っていない。)。
しかるに,被告D医師は,午前零時14分ころの意識消失を単なる失神と誤診して緊急性のある脳内病変であることに気付かず,また,その後のけいれん様姿勢を子癇すなわちお産の病気と誤診し,子癇とのみ告げて脳出血などの脳内病変について告げなかったため,搬送先の確保に長時間を要し,遠方である国立循環器病センターに転送されることになった上,搬入時に産婦人科医が待機することとなり,病状を見て直ちに頭部CT検査が行われ,脳神経外科医が呼ばれて開頭血腫除去術の準備が開始されるという経過をたどり,手術の開始(午前7時55分)が搬入から2時間以上も遅れることとなった。
(被告らの主張)
ア 前記のとおり,Cの右前頭葉の出血が発生したのは8日午前4時ころであるから,午前零時14分ころから数分間が経過した時点で頭部CT検査を実施していても,何の所見も得られなかった。
仮に原告らが主張するとおり8日午前零時ころCに被殻出血が発生しており,午前零時14分ころから数分間経過した時点で経過観察もせずに頭部CT検査の準備に取りかかっていたとしても,帝王切開術を終えて開頭に至るのは午前4時30分ころであり(頭部CT検査の結果が判明するのは午前1時ころであり,その時点で脳出血と判断し,最初に国立循環器病センターに搬送受入れを要請して承諾を得ることができて直ちに搬送を行ったとしても,国立循環器病センターへの到着は午前2時ころとなり,そこから開頭手術まで約2時間30分を要する。),更に血腫部位に到達して血腫を除去するために時間を要することからすれば,午前4時ころ脳ヘルニアが完成するのを回避することはできなかった。
また,瞳孔散大した8日午前2時の時点におけるCの病態が除脳硬直であったとすれば,この時点で中脳・橋の損傷とともに不可逆的な脳ヘルニアが完成していたことになり,治療可能性はなかった。
イ 原告らは,頭部CT検査を実施していれば脳出血の存在が明らかになっており,数多くある脳外科救急機関に搬送できた旨主張するが,Cの脳内血腫の除去手術は,胎児であった原告Bの生命維持のための全身麻酔による帝王切開術を併せて行うことが不可欠であり,そのための産科医や麻酔医,小児科医の管理も必要であった。脳出血があるからといって,脳外科医が産科医や新生児専門の医師による分娩・新生児介護処置を放置して脳ヘルニアをきたした妊婦の脳内血腫除去術を実施するとは考えられない。
したがって,本件において,子癇であれば救急搬送先の確保は困難であったが脳出血の緊急手術であれば確保が容易であったということはできない。
(4)損害
(原告らの主張)
アCの損害
(ア)逸失利益4756万7497円
Cは昭和49年6月1日生まれであり,死亡当時32歳であった。32歳から67歳までの就労可能年数につき,平成16年賃金センサス第1巻第1表産業計・学歴計・企業規模計・全労働者の年間平均給与額446万9300円を基礎とし,生活費控除を35%としてライプニッツ係数を用いて算出すると,逸失利益は次のとおりとなる。
4,469,300 ×(1 - 0.35)× 16.3741 = 47,567,497
(円未満切り捨て。以下同じ。)
(イ)死亡慰謝料2600万円
イ原告Aの損害
(ア)慰謝料500万円
(イ)葬儀費用150万円
ウ 弁護士費用各400万円
エ 相続
Cの損害につき,法定相続人である原告A及び原告Bが2分の1ずつ相続
した。その結果,原告Aの損害額は4728万3748円,原告Bの損害額は4078万3748円となる。
(被告らの主張)争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(甲A1~6,乙A1~11)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実が認められる。
(1) C(昭和49年6月1日生)は,平成17年5月5日に原告Aと婚姻した後,妊娠し,同年12月20日,被告病院を受診し,被告D医師の診察を受けた。その結果,妊娠8週と2日で,出産予定日は平成18年7月30日と診断された。
Cが被告病院を選んだのは,原告らの居住地の近くにある五條病院の産科が閉鎖されていたことや原告Aが被告病院で生まれ,原告Aの祖母が被告病院で看護師をしていたことなどによるものであった。
被告病院産科の診察日は,月曜から金曜までであり,産婦人科医は被告D医師のみであったが,水曜と木曜の診察は,奈良県立医大から派遣されて来る医師が担当していた。また,被告病院産科の手術日は,水曜と木曜であり,被告D医師が奈良県立医大からの派遣医師とともに担当しており,被告病院では対応できない場合には車で30分程度の場所にある奈良県立医大に転送していた。
(2) Cは,平成17年12月20日以後,定期的に被告病院産婦人科を受診していた。診察は,奈良県立医大から派遣されていたG医師が担当していた。
Cは,出産予定日を経過した平成18年8月2日,被告病院を受診し,G医師の診察を受け,予定日の1週間後である8月7日までに分娩が始まらなければ,入院して分娩誘発剤を服用する予定である旨の説明を受けた。Cのそれまでの受診時の血圧は,108/50~118/62程度であり,妊娠高血圧症候群ではなく,このほかにも妊娠経過に特段の問題はなかった。
(3) Cは,8月7日,まだ分娩が始まらなかったため,午前9時20分ころに被告病院に入院し,午前9時40分ころから経口の陣痛促進剤(プロスタルモン)の服用が開始された。この時点の血圧は122/70であった。その後,1時間おきに服用したが,規則的な陣痛はなく,午後2時45分の時点で,予定の6錠を終了したが,まだ陣痛は弱かった。午後6時ころから陣痛は規則的となったが,分娩までにはまだ時間がかかることから,被告D医師はいったん自宅に帰った後,午後11時ころ被告病院に戻り,被告病院内の休憩室で待機していた。
なお,同日の被告病院における当直医は,内科のE医師と整形外科医,小児科医であり,脳神経外科医はいなかった。当直の看護職員は,H看護師(以下「H看護師」という。)とF助産師であった。入院している患者は13名,新生児は4名であった。
F助産師は,午後5時以降随時,陣痛室内のCの状態を観察していた。Cは,痛みをを訴えることが多く,嘔吐もあったが,特に医師に報告を要する程度のものではなかった。また,同日午後9時30分ころから,原告Aが陣痛室内でCの様子を見ていた。
(4)Cは,8日午前零時ころ「こめかみが痛い」と訴えて,頭部右側を何度もたたき,発汗と嘔吐があった。この時点の血圧は155/84,脈拍数は74回/分であった。F助産師は,Cの痛みが尋常ではないことから,休憩室で待機している被告D医師に電話で報告した。被告D医師は,陣痛による血圧の軽度上昇や暑さ,嘔吐による脱水などの体調不良等と判断し,脱水状態の改善を図り体調をよくする目的で生理食塩水の点滴をし様子をみることにし,その旨電話で指示した。F助産師は,被告D医師の指示に従い,生理食塩水500mLの投与を開始した。
F助産師は,午前零時10分ころ,Cに胃液の嘔吐があったため,再度被告D医師に電話で連絡したところ,プリンペラン(むかつき止め)を投与するように指示を受け,その指示に従い,プリンペラン1アンプルを静脈注射した。Cは,この時点では,呼びかけに応じて時々開眼していた。
(5) Cは,午前零時14分ころ,突然意識を消失し,応答しなくなった。F助産師はCの頬をたたいて起こそうとしたが,意識は戻らなかった。F助産師は,自動血圧計を装着するとともに,H看護師に連絡し,H看護師が被告D医師に電話で連絡した。
被告D医師は,すぐに陣痛室に駆けつけたが,Cはベッド上で閉眼しており,呼びかけにも応じない状態であり,失禁していた。血圧は147/73,脈拍は73回/分,SpO2 は97%であり,顔色は正常であった。被告D医師は,H看護師に対し内科当直であるE医師に連絡するように指示した。
E医師は,連絡を受けて陣痛室に駆けつけ,Cの診察をし,JSC100~200(痛み刺激に反応)で,血圧,呼吸は安定しており,瞳孔に散大はなく,対光反射を認め,共同偏視や顔面まひ,チアノーゼはなく,聴診で胸部に異常もなかったことから,陣痛による精神的な反応から来る心因的意識喪失発作であり,バイタルサインがよいのでこのまま様子をみるのが相当であると判断し,被告D医師に対しその旨告げた。なお,E医師は,この時点までに脳梗塞と脳出血を合わせて約100例の診察経験があった。
被告D医師は,まもなく,原告Aに対し,「内科の先生に診てもらったが,失神と思われるとのことで,全身状態はよいのでこのまま様子をみることにした。」と説明した。そして,被告D医師は,胎児心音が正常であることを確認した後,休憩室に戻り,E医師も陣痛室から出た。被告D医師らは,H看護師やF助産師に対し特に指示はしなかった。
(6) F助産師は,以後,10分に1回程度の割合で陣痛室を訪れ,Cの血圧測定や胎児の心音聴取などを行ってCの様子を観察していた。血圧の推移は,午前零時25分ころ148/69,午前零時30分ころ156/71,午前1時ころ152/84であった。また,F助産師は,午前零時40分ころ,Cに分娩監視装置を装着した。胎児の心拍数は150~160回/分であった。Cは,午前1時ころ,声掛けに対して応答がなく,意識がない状態が続いていたが,陣痛発作時に四肢を動かしたり,顔をしかめたりしていた。脈拍は74回/分で,胎児の心拍数も正常であった。Cはその後も意識が戻らない状態が続いていた。
この間,H看護師は,新生児に授乳させるなどをしており,陣痛室には行っていなかった。
(7) 午前1時37分ころ,H看護師とF助産師は,ナースステーションにいたが,そこに設置されているCの自動血圧計のモニターが175/89と高値となったことから,二人で陣痛室に赴いた。
Cは,いびきをかいており,腕をぐーっと外側に伸ばし,けいれん発作が生じていた。水銀血圧計で計ると200/100であった。H看護師は,原告Aに対し,「いつからこのような状態なのか」と問うと,原告Aは「少し前から」と答えた。なお,Cのこのときの状態について,H看護師は,それまでの経験から除脳硬直であると判断し,病棟看護管理日誌(甲A3・2頁)に「除脳硬直」と記載し,F助産師は「全身にぐうっと,四肢というか,手足に力を入れて,つっぱったような形で反り返ったような姿勢」(証人尋問での証言・証人尋問調書10頁),原告Aは,「両腕を内にぐっと曲げて,同時に両足の爪先をぴっと伸ばす感じで,20~30秒くらい続いて3,4分ごとに繰り返す。」(本人尋問での供述・本人尋問調書15頁)との認識であった。
F助産師は,すぐに被告D医師に連絡をし,被告D医師は急いで陣痛室に駆けつけた。被告D医師が入室した時点でのCの様子は,ベッドに仰向けに寝て,手足をつっぱり,首も背中も反り返ったような状態で,けいれんしていた。瞳孔は,左右差はなく,共同偏視もなかったが,中程度の散大固定があり,対光反射もなかった。被告D医師は,子癇による強直性けいれん(筋肉の攣縮が継続的に起こるけいれん)ではないかと考え,子癇発作に対する鎮痙剤であるマグネゾールの静脈注射を指示するとともに,E医師を呼ぶように命じ,この時点で高次医療機関への転送を考えた。なお,被告D医師は,この時までに24年の臨床経験を有し,約6000件の分娩の経験があったが,子癇の経験は3例程度であり,脳出血の経験はなかった。
午前1時46分ころ,Cに対しマグネゾールが静脈注射され,その後,舌をかまないようにバイトブロックを口にかませた。
E医師は,午前1時50分ころ,陣痛室に駆けつけCを診察した。血圧,呼吸状態は安定していたが,瞳孔は散大し,右の対光反射は消失し,左の対光反射をわずかに認めるのみであった。E医師は,こうした所見や約1時間30分意識消失状態が続いていることから,脳に何らかの異常を来しているものと考え,被告D医師に対し頭部CT検査を行って脳の状態を調べるかを尋ねたが,被告D医師は直ちに転送したほうがよいと考え,受入依頼を連絡するために,陣痛室を出て電話があるナースステーションに向かった。陣痛室ではE医師とH看護師,F助産師がCの観察にあたった。なお,被告病院では,夜間CT検査を実施する場合,実施を決めてから現実に実施するまでに準備のために40~50分程度を要していた。
(8) 被告D医師は,午前1時50分ころ,奈良県に導入されている奈良県周産期医療情報システムに則って,奈良県立医大に電話をかけ,Cの受入れを依頼した。奈良県立医大では,満床であり,受け入れることができなかったため,他の病院を探して見つかった時点で連絡するとのことであった。被告D医師のそれまでの経験では,搬送先は長くても1時間程度で決まっていた。原告Aは,このころ,原告AやCの両親らに電話で異常事態になっていることを連絡した。
(9)F助産師は,午前2時ころ,Cの瞳孔が開いており,対光反射がないこと
を確認した。血圧は148/75,呼吸数は26回/分であった。
午前2時すぎに原告Aの家族が,午前3時すぎにCの家族が被告病院に到着した。
被告D医師は,ナースステーションに置かれているCのモニターの自動血圧監視装置や分娩監視装置の数値を見ながら,搬送先病院への紹介状を書き,電話を待っていた。なお,被告D医師は,診療情報提供書(乙A2・7頁)の「病名・仮診断」欄に「子癇の疑い」と記載し,説明として「昨日,予定日超過の為入院。プロスタEカプセルにて誘発施行の患者ですが,本日午前零時頭痛出現し,血圧155/84でしたが,意識消失となりました。バイタルサイン良好の為経過観察と致しましたが,午前1時37分血圧200/100と上昇し,強直性ケイレンを認めました。現在マグネゾール25mL/時,血圧150/80の状態です。」と記載している。
Cは,午前2時ころから3時ころにかけて,間欠的にけいれんが出現し,また,いびきがあり,時々強くなる状態であった。午前2時40分ころ,F助産師から連絡を受けてI看護師長が被告病院に到着し,看護に加わった。
被告D医師は,午前2時45分ころ,原告Aやその家族に対し,「子癇の疑いが強く,薬を使って対処しているが,この病院ではこれ以上の医療行為はできず,奈良県立医大に搬送を依頼した。搬送先が決まるまで待ってほしい。」と説明した。
午前3時ころ,被告D医師は,奈良県立医大からいっこうに連絡がないので,奈良県立医大に電話をかけたが,まだ見つからないとの返答であった。電話の途中で,原告Aの父が被告D医師から受話器をとって,「廊下でもいいからとにかく受け入れてほしい。」と頼んだが,奈良県立医大では受入れはできないとの返答であった。
搬送先が決まらないことから,Cの父が以前大阪市消防局に勤務していたことがあり,携帯電話で大阪市消防局の救急隊に電話をかけて,数か所の病院の電話番号を聞き,被告D医師に伝えた。被告D医師は,奈良県立医大を通じて搬送先を依頼していることから,別のルートで搬送先を探すことに消極ではあったが,家族から強い依頼を受けたため,救急隊から聞いた病院数か所に電話をかけたが,いずれも断られた。
I看護師長は,まだ搬送先が決まらなかったが,決まった場合直ちに搬送できるようにF助産師に指示し,午前3時49分,中吉野広域消防組合消防本部に対し救急車の出動を要請した。救急車は午前3時56分に被告病院に到着し,待機していた。
午前4時ころからE医師もナースステーションに入り,被告D医師とともに搬送先の状況の把握に努めた。
午前4時5分ころ,Cのいびきは強くなり,血圧は176/77,脈拍133回/分であった。
被告D医師は,原告AやCの家族からの要請を受けて,また奈良県立医大に電話をかけ,奈良県立医大での受入れを依頼したが,やはり奈良県立医大では受入れができないとの回答であったものの,県立奈良病院に直接依頼の電話をかけると受け入れてもらえるかもしれないとの情報を得た。このため被告D医師は,県立奈良病院に電話をかけて受入れを依頼したが,応じてもらえなかった。
(10) そのころ,国立循環器病センターでは,大阪府立母子総合医療センターから,次いで,奈良県立医大から相次いで,Cについて子癇の救急患者であるとの連絡を受け,受け入れることを決め,その旨の連絡が大阪府立母子総合医療センター及び奈良県立医大から被告病院にされた。
搬送先が決まった午前4時30分ころ,Cは,呼吸困難な状態に陥り,H看護師から連絡を受けたE医師がまず陣痛室に向かった。Cには舌根沈下の症状が出現しており,遅れて駆けつけた被告D医師が補助して,Cに対し気管内挿管を行った。それにより自発呼吸を認めた。
(11)午前4時49分,救急車で国立循環器病センターへの搬送が開始され,救急車には,被告D医師,F助産師,原告Aらが同乗した。搬送時のCの状態は,呼吸20回/分,血圧163/99,脈拍123回/分,意識状態JCS300(深昏睡)で,自発呼吸は残存していたが,瞳孔が中等度散瞳して固定しており,両側の瞳孔が5㎜で対光反射はなかった。胎児心音は異常はなかった。
救急車は,午前5時47分,国立循環器病センターに到着した。その時の状態は,血圧が182/114,SpO2 が98%,気管内挿管状態で自発呼吸は認められたが,JCS300であり,瞳孔は両側とも散大固定し,対光反射なしの状態であった。国立循環器病センターの産婦人科のJ医師(以下「J医師」という。)は,Cの状態を見てすぐに脳出血を疑い,直ちに脳神経内科に連絡した。他方,被告D医師は,被告病院での診察日であるため,午前6時15分に乗ってきた救急車で被告病院に戻った。
(12)国立循環器病センターにおいて午前6時20分ころCに対し実施された頭部CT検査(乙A4)によると,右被殻から右前頭葉に及ぶ巨大脳内血腫(約7× 5.5 × 6 ㎝)が認められ,著明な正中偏位があり,脳幹部にも出血が認められ,脳室穿破を伴うと診断された。臨床症状,CT所見とも脳ヘルニアが完成した状態であった。基底核部の血腫の量から考えて,出血源は基底核部であり,その一部が中脳部にも穿破したものと考えられた。CT検査結果を検討した脳神経外科のK医師(以下「K医師」という。)は,この状態で手術をしても救命できる可能性は極めて低いと考えたが,いつころ脳ヘルニアが完成したかなど詳細が不明で,仮に脳ヘルニアの完成から時間が短ければ,救命だけは可能性も否定できないこと,原告Aらから強い要望があったことなどから,緊急開頭による血腫除去術を行うことにした。他方,胎児の状態は,脈拍の基線が180と頻脈であり,基線細変動が減少しており,低酸素状態の可能性が高いことから,帝王切開術も行うことになった。これらの手術は,並行して行うことにし,家族への説明と手術準備が進められ,Cは,午前7時15分ころに手術室に入り,全身麻酔が開始された。術前に頭蓋内の血管系精密検査は行われなかった。午前7時55分ころ,Cに対する開頭血腫除去術及び帝王切開術が開始され,午前8時4分,原告B(2612グラム)が出生した。
手術中の所見は,次のとおりである。硬膜の緊張が非常に高く,前頭葉部分で硬膜切開を開始すると,脳実質の局所的脱出に引き続いて血腫の漿液成分が脳表に穿破し噴出した。これによりやや脳圧は低下し,放射状硬膜切開を行った。脳表に明らかな赤色静脈等は認めなかった。血腫穿破が起こった前頭葉部分に皮質切開を行い,ここから凝血塊を吸引・除去していった。ある程度吸引除去した後,後方・上方の凝血塊をたぐり寄せると一塊として大きな血腫が摘出された。前下方の血腫周囲には血管成分がやや多く,易出血性であった。血管奇形等検索の時間的猶予のない減圧目的の手術であることにかんがみ,この部分の血腫除去は一部分に留めた。血腫の大部分を除去し,血腫腔の止血を行ってサージセルを敷いた。右脳には既に甚大なダメージが起こっているものと推定されたが,一応の拍動が観察された。脳表に心膜用ゴアテックスを敷き,硬膜を戻すなどの措置を講じ,皮膚を全層縫合して午前10時に手術を終えた。
(13)Cは,手術により,大部分の血腫は除去されたが,既に脳の損傷は甚大であり,瞳孔散大状態も不変で,意識を回復することなく,手術から8日後の16日に死亡した。死因は脳内出血と判断された(解剖検査は,原告Aらが希望せず,実施されなかった。)。
なお,原告Bは,現在順調に育っている。また,被告病院では,本件があった後,分娩を扱うことを中止し,現在,奈良県南部には分娩施設がない状況となっている。
2 医学的知見
以下に掲げた各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の医学的知見が認められる。
(1)脳の構造(乙B7)
脳の構造及び各部位の概観は,別紙1及び2のとおりである。
脳は,小脳テントと大孔の二つの開口部があり,それぞれの開口部の上に,大脳・間脳を中心とする2階部分と,小脳・橋・延髄を中心とする1階部分があり,中脳は階段に相当し,左右の大脳半球は大脳鎌で分かれている。大脳基底核は,大脳半球の基底部の髄質にある神経核の集合体であり,被殻を含む。脳の覚醒を維持するのが脳幹を中心とする脳の中軸構造(脳幹,視床下部,視床)である。脳を木にたとえると,脳幹が幹で,大脳や小脳は枝葉といわれている。
(2)妊娠高血圧症候群(乙B8)
妊娠高血圧症候群とは,妊娠20週以降,分娩後12週までに高血圧がみられる場合,又は,高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで,かつ,これらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によるものではないものをいう。
従来妊娠中毒症として定義・分類されていたが,平成17年4月の日本産婦人科学会総会にて審議決定後,日本産婦人科学会の統一見解となった。
(3) 子癇(甲B1,6,乙B6,9,18,22,26の2,34,36,41,42,L鑑定)
子癇は,妊娠20週以降に初めてけいれん発作を起こし,てんかんや二次性けいれんが否定されるものをいうと定義されている。
子癇は,通常,顔面のひきつけに始まり,速やかに四肢から全身に広がって筋が収縮する強直性けいれん(拳を強く握り,腕は曲げ,下肢は強く進展)となる。開始から15~20秒すると,今度は下顎,顔筋,四肢が収縮と弛緩をすばやく繰り返す間代性けいれんが約1分持続する。その後けいれん発作は終了して昏睡状態が数分~十数分続くが,まもなく覚醒する。ただし,重症例では,次々と起こるけいれん発作中も昏睡が持続し,覚醒することなく,死の転帰をとる場合もある。
子癇の発生頻度は,0.15%~0.45%と報告されている。子癇は突然起こるが,頭痛(32.4%),視覚障害(23.5%),嘔気・嘔吐(20.6%)などの前駆症状がみられる。子癇は,特例を除けば,妊娠高血圧症候群に引き続き起こる。重要な点は,妊娠高血圧症候群発症から子癇発症までの期間は短いものが多く,急速に妊娠高血圧症候群が悪化して発症すること,子癇発作1週間前までの妊娠高血圧症候群は軽症,無症状の例もあるが,子癇発作直前の妊娠高血圧症候群はほとんどが重症化しており,特に高血圧との関係が深いことである。
子癇は,他のけいれんを起こす疾患(脳出血,脳梗塞等)と鑑別する必要がある。特に,脳出血,くも膜化出血との鑑別は早急に行うことが重要である。すなわち,できるだけ早期に頭部CT検査をし,可能なら引き続き頭部MRI検査を行うことが望ましい。その理由は,緊急手術を要する超急性期の脳出血の診断にはMRIよりもCTのほうが有用で,しかも短時間に撮影可能である(MRI検査も行えば脳梗塞かどうかの診断も可能である。)からである。脳出血所見がなければ子癇に対する治療を行う。
子癇発作を抑制し再発を予防するための治療薬としては,安全で最も効果的とされているのが硫酸マグネシウム(商品名マグネゾール)である。マグネシウムイオンが持つ中枢神経抑制作用や神経筋接合部における神経伝達抑制作用が抗けいれんに働くものと考えられる。典型的な例では,初回投与4g(40mL)でけいれんは停止し,1~2時間以内に妊婦は意識を回復する。
(4)除脳硬直と除皮質硬直(乙B21)
除脳硬直は,中脳と橋が両側性に障害され,延髄と大脳,間脳との連絡が断たれた状態でみられる現象である。除脳硬直では,四肢の筋肉は著しい過伸展を呈し,回内位をとるとともに,手関節は強く屈曲,足関節は強く底屈する。除脳硬直の基礎疾患としては,脳血管障害や脳腫瘍が多く,脳ヘルニアの重要な兆候として知られている。
除皮質硬直は,内包と隣接する大脳基底核や視床が広範に障害された場合に生じる。脳幹は障害されていない。除皮質硬直では,肩関節は内転して両上肢は肘で屈曲する。両下肢は,除脳硬直と同様に,強く伸展する。除皮質硬直の基礎疾患は,さまざまであるが,脳血管障害,脳腫瘍,無酸素脳症,脳炎などでみられる。
(除脳硬直と除皮質硬直の状態につき,乙B21の図参照)
(5) 脳内出血及び脳ヘルニア(甲B2,3,4の4~7,乙B4,5,7,11,12,19,26の2,M鑑定)
ア 概観
脳内出血は脳内に出血する疾患である。脳組織は,頭蓋骨及び硬膜により各部分に分けられているが,その一つが出血などの病変によって容積を増すと,頭蓋内の他の部分との間に組織圧格差が生じ,脳組織が圧格差に応じて移動し,脳ヘルニアを起こす。具体的には,脳内に生じた出血などの異物のために脳は圧迫され,固い頭蓋骨の内面に押しつけられる状態になり(頭蓋内圧亢進,頭痛) ,嘔吐,意識障害などの症状を呈する。出血などの病変が生じた部位の脳組織は破壊されるためその部の機能低下が起こり,まひ,感覚障害等の局所症状あるいは巣症状が生じる。被殻出血であれば,通常,被殻の内側に存在する内包(大脳皮質の運動領からの運動神経伝達路が扇のかなめ状に集まる部位)を圧迫・破壊するため,巣症状としては,出血とは反対側のまひを呈する。同時に病変部を通過している神経伝達路が断たれるため,情報伝達は停止あるいは迂回ぜざるを得なくなり,刺激に対する反応が遅れたり,誤った言動をするようになる。大脳基底核(被殻)からの出血が少量あるいは中程度にとどまっていれば,意識は保たれてまひや言語障害にとどまる。疾患が増大すると,脳容積は増大し,固い頭蓋骨に自らを押しつけ頭蓋内圧が高くなり,脳機能は全体的に低下し始める。最終的に,機能低下は脳幹に及び,意識障害から呼吸中枢障害に至り呼吸が停止する。
なお,頭蓋内血腫などで急に頭蓋内圧が上昇すると,脳血流が低下するが,脳には常に脳血液量を保とうとする生体調節機能があるので,心拍出量の増加やその他の化学的調節機構により自動的に,頭蓋内に血液を無理にでも押し流そうとする生理的な力が働き,全身血圧が上昇する。このように,頭蓋内圧の急激な上昇時に血圧が上昇する現象をクッシング現象という。
分娩中に脳出血が起こるのは,0.007%程度であると報告されている。
イ 脳ヘルニアの進行過程
ヘルニアの発生は,病変の増大速度も関係する。例えば,比較的小さな病変でも急速に容積が増大すると脳ヘルニアを起こし得るし,髄膜種のように大きな病変でも増大速度が遅ければ,脳は圧変化に対応できる。テント切痕から離れたテント上部分から下方向に圧迫が加わってくると,まず障害されるのは間脳であり,ついで中脳,橋,延髄と障害が及んで死亡に至る。
脳ヘルニアの進行過程は,間脳期,中脳-上部橋期,下部橋-上部延髄期,延髄期の4期に分けられる。
(ア)間脳期
この時期に起こる主な変化は,意識内容及び動作の変化であり,JCS1桁(刺激しないでも覚醒している状態)から始まり,この時期の最後にはJCS100(痛み刺激に対してはらいのけるような運動をする)まで低下してくる。呼吸は不規則になり,深いため息やあくびなどがまじってくる。視床下部にある瞳孔散大線維が虚血や浮腫で障害されるため,瞳孔は小さい(1~3㎜)が注意してみれば対光反射はあり,眼球運動は保持されている。運動まひは両側に現れる。この時期でもかなり進行すると,病側と反対側上下肢は疼痛刺激に対し除脳姿勢を示し,病側と同側の上下肢は除皮質姿勢を示してくる。この時期は,可逆的であり,また回復可能である。この時期に対処できるかが勝負の時とされている。
(イ)中脳-上部橋期
意識レベルは既にJCS200(痛み刺激に対して手足を動かしたり,顔をしかめたりする)から一部300(痛み刺激に反応しない)に低下してくる。体温の変動が顕著となり,呼吸は徐々に持続性の大きく深い呼吸(中枢性神経原性過換気)に変わってくる。小さかった瞳孔も中等度に拡大(3~5㎜)し,不規則な形となり,対光反射は消失する。疼痛刺激に対しては,除皮質姿勢から両側とも除脳姿勢へと進行してくる。この段階では,通常非可逆的であり,小児を除いて,予後は非常に悪く死亡するか遷延性意識障害となる。
(ウ)下部橋-上部延髄期
意識レベルは既に300にまで低下し,痛み刺激に対する運動反応は全くみられず,全身の筋緊張は弛緩性となる。呼吸状態は,中枢性神経原性過換気からむしろ正常呼吸に類似した呼吸となる。この段階では,非可逆的であり,回復は望めない。
(エ)延髄期
瞳孔は散大し,対光反射はない。呼吸の中枢は延髄にあるので,延髄が損傷されると,呼吸の深さ,回数とも不規則となり,血圧低下,脈拍の不規則化が起こり,最終的に呼吸は停止する。
ウ 脳ヘルニアとJCS
脳ヘルニアとJCSとの関係をまとめると,JCS1桁の意識障害は,圧迫がまだ間脳ないし中脳に及んでいない状態で,生死に関する限り安全な状態である。これに対し,2桁の意識障害は,上方,側方からの圧迫が既に間脳から中脳に及んでいることを示唆し,緊急レベルで外科的減圧術を施行しなければならず,この時期に適切な治療を行うと結果は一般的に良好である。JCSが3桁,特に200~300になると,間脳や上位脳幹部に存在する網様体が障害されていることを示唆し,したがって,下位脳幹部に存在する生命中枢は風前の灯であり,いかなる治療をしても予後はよくない。
また,脳ヘルニアと救命可能性との関係については,脳出血から瞳孔散大まで時間があるような病態がゆっくりと進行した場合には脳ヘルニアが完成してもある程度の時間までは救命可能であるが,急激に病態が進んだ場合には,脳ヘルニアが完成してわずかな時間で救命不可能となる。
エ 研究報告
(ア)J医師らによる妊娠関連の脳血管障害の発症に関する研究(平成18年)は,妊娠に関連した脳血管障害について,全国の約4800の施設・診療科へのアンケート調査の結果を分析したものであり,次のとおり報告している(乙B26の2)。
脳出血の初発症状は,意識障害が最も多く,66.7%で認められ,次いで,頭痛(56.4%),けいれん(23.1%),まひ(23.1%)であり,脳出血のような出血性脳血管障害では,頭痛とともに意識障害が初発症状として現れやすいことが示された。子癇・高血圧性脳症では,当然けいれんが最も多く79.3%で認められた。まひは1 例もなかったが,意識障害(46.8%),頭痛(28.0%)も認められる症例が少なくなく,出血性脳血管障害との鑑別が必要になる。脳出血と診断(CT検査)までの時間についてみると,出血から3時間以内の場合,25例中7例で予後が良好であり,17例は予後不良でうち2例は死亡した(1例は不明)。診断まで3-24時間であった10例は,うち5例が予後不良であった。予後良好率のみに注目すると早ければ早いほど予後が良好というわけではないが,3-24時間の群での予後不良は全例が死亡である。診断までの時間が3時間を超えると死亡率が上がることがわかる。脳出血とJCSの関係については,脳出血の場合,受診時のJCSと予後は強い関連を示した。JCSが0又は1桁の場合,予後不良例は19例中5例であったが,JCSが2桁になると予後不良例は4例中3例,3桁では15例全例が予後不良であった(うち5例は死亡)。
(イ)平成2年に発表された金谷春之医師の論文(昭和59年~昭和61年の外科的治療3372例の解析結果報告)によると,被殻出血があり外科的治療をした場合の死亡率については,5段階に分けた整理がされており,次のとおりである(甲B4の7)。
1 意識清明又は混乱(JCS0又は1桁)8%
2 傾眠(JCS10)11%
3 昏迷(JCS20,30)20%
4a 半昏睡(脳ヘルニア徴候を伴わない,JCS100)33%
4b 半昏睡(脳ヘルニア徴候を伴う,JCS200)59%
5 深昏睡(JCS300)81%
オ 脳卒中治療ガイドライン2004
脳卒中治療ガイドライン2004は,脳出血の手術適応について次のとおり定めている(甲B4の6,乙B4)。
被殻出血の手術療法は重症例の救命を目的とする時にのみ有用であることか示されており,血腫が大きく(31mL以上),圧迫症状がみられる患者では手術の効果を示唆するものが多い。
視床出血については,血腫の量によってはまひや意識障害の改善に有効との意見もあるが,556例についての検討では,手術治療は重症例に対する救命効果しかなく機能予後は改善しなかった。
脳幹出血においては,手術治療の無効性が確認されている。
(6) 意識障害患者の初期治療と鑑別診断(甲B2,4の4,乙B36,41)
ア 救急診療の場において,重症の意識障害患者はその対応に高度な判断力と緊急性を要求され,処置が遅れると死につながるし,治療が奏効しなければ重篤な神経脱落症状を残す。一方,意識障害の原因となる病態は多種多様で,経験を積んだ臨床医にとっても原因診断は容易ではないことも多い。
頭蓋内に意識障害患者の中でも脳出血,くも膜下出血等の確定診断には,画像診断が必須であるが,呼吸・循環の不安定な状態での施行は慎まなければならず,一見落ちついている患者でも,検査に出室させることによるリスクや検査中不測の事態をも考慮し,その種類と施行時期(反復検査を含めて)を慎重に選択することが重要である。
イ 意識障害者が妊婦である場合には,行うべきことは,
1)バイタルサインのチェック(血圧,脈拍,呼吸,意識レベル)
2)気道,血管の確保
3)血液検査
4)尿検査
5)胎児の状態の把握
6)けいれんのある場合はけいれんの鎮静
7)頭部CT,MRI検査等がある。
1から6までができたら,胎児心拍モニタリングを行いながら,家族にどのような状況で意識障害が起こったかを問診する。けいれんを伴う場合は,まず子癇発作を考える。
ウ CT検査により,脳出血の部位診断はもちろん,血腫の量,脳浮腫,脳室穿破の程度まで診断できる。脳出血は急性期には高吸収域として描出される。発作から数時間以内に検査された場合には,血腫の増大がみられることもあるので,必ず再検査が必要である。
エ 妊娠中にけいれん発作を起こした場合,脳血管障害(子癇,脳出血,脳梗塞)が原因として最も考えられ,症状は,頭痛,けいれんで,特に出血では激しい頭痛,頂部硬直を認める。子癇以外の脳血管障害はまれであるが,生じた場合には,極めて重篤であり,しかも予測しにくい合併症である。子癇と他の脳血管障害との鑑別は困難であるが,局所の脳神経異常症状,持続する昏睡,さらに硫酸マグネシウムに奏効しない症例は子癇発作以外の病態を推察し,脳画像診断と神経学的検査などによる鑑別診断が求められる。現状では,診断の遅れや誤診の可能性は回避しにくく,また最近の有力な治療方法を用いても予後の改善が得られるとは言いがたい。
(7)奈良県周産期医療情報システムの概要(乙B30)
奈良県では,周産期医療に必要な情報を一元的に収集し,迅速かつ的確に提供することにより,周産期医療設備等の有効かつ効率的な活用を支援するものとして,平成8年3月から奈良県周産期医療情報システムの運用が開始されている。24時間体制で,周産期医療の協力病院の空きベッド等をネットワーク上で把握し,妊婦や新生児の転院搬送をするものである。
周産期医療実施病院は,奈良県立医大,県立奈良病院,近畿大学医学部附属奈良病院,天理よろづ相談所病院であり(当初は,ほかに市立奈良病院があったが,現在周産期医療は休止中である。),周産期患者が発生した場合,かかりつけの医療機関は,奈良県立医大又は県立奈良病院に電話で照会し,当該病院で受入れが可能であれば受け入れ,受入れができない場合,電話を受けた奈良県立医大又は県立奈良病院が奈良県周産期医療情報システムにより検索して他の医療機関で受入れが可能かを調べ,可能な医療機関をかかりつけ医療機関に回答する。奈良県周産期医療情報システムでは受け入れができない場合は,奈良県外の医療機関に個別に照会し,見つかった医療機関を照会先の医療機関に連絡する。
平成9~10年の調査によると,母体搬送依頼があったのは,369例であり,210例(56.9%)は県内で収容されたが,159例(43.1%)は近隣の府県へ搬送された。そのうち奈良県立医大への母体依頼があったのは212例であり,うち103例(48.6%)は自ら(奈良県立医大)で受け入れ,34例(16.0%)は県立奈良病院に搬送された。両病院とも受入れができない場合には,県内の他の医療機関,さらには県外の医療機関を探すことになるが,県外の場合,まず距離的に近い大阪府の医療機関を探し,大阪府での受入れが不可能な場合には,兵庫県や三重県に搬送することもあり,遠方の施設で収容された場合には,母体搬送依頼があってから3,4時間を経過している場合もある。
3 争点1(Cの臨床経過)
(1)1で認定した事実関係に基づき,2で認定した医学的知見に照らし,Cの臨床経過について検討する。
Cは,8日午前零時ころ,突然に激しい頭痛が頭部右側に起こり,嘔吐を伴い,血圧が155/84であったところ,脳内に生じた出血などの異物のために脳が圧迫されると,固い頭蓋骨の内面に押しつけられる状態になり,頭痛,嘔吐,意識障害などの症状を呈し,頭蓋内圧亢進に伴う血圧上昇(クッシング現象)が起こることからすると,この時点で激しい出血が右脳に生じたと認めることができる。
午前零時14分ころに突然意識をなくし,起こそうとしても意識が戻らなかったことは,大脳基底核からの出血が少量あるいは中程度にとどまっていれば意識は保たれてまひや言語障害にとどまることからすると,かなりの量の出血があり,この時点で中脳まで血腫が及んだものと考えられ,脳ヘルニアが進行している状態であるといえる。そして,まもなくJCSが100~200の状態となり,それ以降も意識障害が続き,午前1時37分ころには,血圧が,自動血圧計で175/89,水銀血圧計で200/100となり,けいれん発作,いびき,硬直性のけいれんの症状が出現している。この症状について,H看護師は除脳硬直と判断し,病棟看護管理日誌にその旨記載し,F助産師は,「全身にぐうっと,四肢というか,手足に力を入れて,つっぱったような形で反り返ったような姿勢」と証言し,原告Aは「両腕を内にぐっと曲げて,同時に両足の爪先をぴっと伸ばす感じで,20~30秒くらい続いて3,4分ごとに繰り返す。」と供述しているところ,前記の医学的知見に照らし,除脳硬直であると考えられる。したがって,この時点では既に中脳と橋が両側性に障害されていたことになる。
午前1時50分ころの時点では,瞳孔は散大し,右の対光反射は消失し左はわずかに認めるという状態であり,脳出血を形成した右側脳が先にヘルニアに完成し,左脳もヘルニアには陥っているが,完成までには至っていない状態と考えられる。
午前2時ころには,瞳孔が散大しているほか,呼吸が26回/分と過換気の状態となり,呼吸障害も起こってきていると考えられる。この状態になると,脳ヘルニアの進行過程における「中脳-上部橋期」に相当し,通常非可逆的である。この段階でも,ただちに救命不可能となるものではないが,午前零時ころからの出血で午前2時ころには既に瞳孔散大の状態に至っているのであるから,Cの病態の進行は急激であって,午前2時ころから数十分以内に開頭手術を行わないと救命は不可能であった(K医師の証言,証人尋問調書18,22頁)。
(2) Cの臨床経過について以上のように認定することができるが,その理由について,補足する(以下,鑑定人Mの意見を「M鑑定」,鑑定人Lの意見を「L鑑定」,国立循環器病センターのJ医師の陳述書(乙A6)及び証言を「J証言」,K医師の陳述書(乙A5)及び証言を「K証言」,原告が提出したN紀和病院脳神経外科・救急科医師の鑑定意見書(甲B4の1)を「N意見」,O金沢大学附属病院産婦人科医師の鑑定意見書(甲B5)を「O意見」という。)。
ア まず,脳出血の時期について,M鑑定は,午前零時ころであるとし,L鑑定も,午前零時ころにCT検査等が実施されていないので正確な判定はできないとしながらも,急激な状態変化からその時期の可能性が高いと述べており,J証言も同旨の意見であって(K証言も午前零時14分ころと述べるが,午前零時ころの可能性を否定できないとしている。),Cの当時の状態からして,前記のとおり,午前零時ころにCに脳出血が発症したものと考えることができる。
これに対し,N意見は,右脳出血を起こした時期は午前1時37分ころであるとし,その根拠として,午前零時ころに大きな脳出血が起こっていたとすると午前1時ころの時点で患者が陣痛発作時に四肢を動かすことはあり得ないことを述べる。確かに,通常の被殻出血では,被殻の内側に存在する内包(大脳皮質の運動領からの運動神経伝達路が扇のかなめ状に集まる部位)を圧迫・破壊するため,巣症状としては,出血とは反対側のまひを呈するものであるが,Cは,激しい出血があったと考えられる午前1時ころの時点でも,F助産師の診察では四肢を動かしており,まひはなく,通常の被殻出血とは異なるものと考えることができる。しかし,午前1時ころの時点でもまひを呈さなかったのは,脳出血の形成が運動神経伝達路を破壊していないためと考えられる。すなわち,脳出血は,被殻に始まり,運動伝達神経路の外側を上方に進展し,前頭葉の前方に進み,結果的に,巨大脳内血腫(約7 × 5.5 × 6 ㎝)を右被殻から右前頭葉に形成した後,下方に進展し,視床から中脳に穿破したと考えると,午前1時ころの時点において,運動障害が生じていなかったとしても,既に脳出血が生じていることとなんら矛盾するものではない(M鑑定)。他方,脳出血の発症時が午前1時37分ころであるとすると,それ以前の意識消失について合理的な説明ができず(N意見は,「けいれん発作を伴うのは子癇といわれているので,意識消失は高血圧性脳症による意識障害が最も考えられる。」と述べるが,けいれん発作が子癇によるものといえないことは次に述べるとおりであり,Cはこれまで高血圧症はなく,午前零時ころの血圧は155/84であって,意識障害を生じさせるような危険レベルとはいえず,高血圧性脳症による意識障害とは考えにくい。),N意見は前記認定を左右するものではない。
イ 次に,午前1時37分ころのけいれん発作について,原告らは除脳硬直であると主張し,被告らは子癇であると主張するところ,子癇の場合はまずけいれん発作が生じその後に意識障害が生じるのが通常であるところ,午前零時14分ころからの長時間の意識障害後に初めてけいれん発作が生じていること,子癇は高血圧と強い関連性を有しており,子癇発作直前の妊娠高血圧症候群はほとんどが重症化しているものであるところ,Cには妊娠高血圧症候群の既往がないこと,子癇では神経まひが生じることはないが,Cには子癇では生じない瞳孔異常が生じていることなどの各事実や,J医師は明確に子癇を否定していること(J証言・証人尋問調書32,46頁)などからすると,午前1時37分ころのけいれん発作が子癇によるものである可能性は低く,脳出血に伴う除脳硬直と認めることができる。
なお,L鑑定は,子癇に伴い脳出血が起こった,脳出血の症状としてけいれんが起こったの二つが考えられ,その正確な判定は困難であるとし,産婦人科医の立場からは子癇と脳出血が合併した状況と考える旨述べるが,午前零時ころに脳出血を発症し,血圧の経過等からして脳出血で説明できるのであれば,一元的に脳出血として説明できることも指摘しているところであり,上記認定と矛盾するものではない。
ウ 原告らは,Cは,午前3時ないし4時の時点では,痛み刺激に対する反応があり,JSC200,瞳孔4~5㎜で中等度固定,呼吸正常であり,国立循環器病センター到着時の午前6時ころの時点でも,瞳孔は5㎜であり,散大固定には至っていなかったのであるから,午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば,十分に救命できたと考えられる旨主張し,N意見は「国立循環器病センタ, ーにおけるカルテによると,午前6時の時点で『瞳孔中等度散瞳し固定』とあり(乙A3・15頁),この時点でも脳ヘルニア末期のような瞳孔散大に至っておらず,自発呼吸も保たれていたのであり,午前1時37分ころに脳出血を発症したが,午前4時すぎころに患者の状態が悪化したのであって,午前2時時点で脳ヘルニアが完成していたことはない。」旨述べる。
しかし,まず,国立循環器病センターのカルテに記載されている午前6時ころの瞳孔の中等度散大や5㎜の記載は,厳密に瞳孔が5㎜であったというものではなく,左右差がなく,対光反射が消失している状態であり,瞳孔が散大であったという趣旨であって(診療録の3頁の「現病歴及び入院・転科後の経過」中の「経過」欄及びK証言・証人尋問調書31頁),いまだ脳ヘルニアの状態が「中脳-上部橋期」にあることを意味しているものではない。午前6時20分ころ実施された頭部CT検査において,右被殻から右前頭葉に及ぶ巨大脳内血腫(約7 × 5.5 × 6 ㎝)が認められ,著明な正中偏位があり,脳幹部にも出血が認められ,脳室穿破を伴うと診断されており,前記脳卒中ガイドラインに照らすと,既に手術をしても無効であるとされている状況であったといえる。そして,午前1時37分ころの除脳硬直は既に中脳と橋が両側性に障害されていることを示しており,午前2時ころには,瞳孔が散大し,呼吸が26回/分と過換気の状態となっていたのであるから,原告らが主張するような午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば十分に救命できたとは考えられない。
エ なお,そもそもCが午前零時ころに突然脳出血を発症した原因について検討する。国立循環器病センターにおける手術は,巨大血腫による頭蓋内圧亢進に対する緊急減圧術(血腫除去術)であり,出血源を確認する余裕はなく,手術では出血原因を確認できていない。脳出血の原因としては,高血圧性脳内出血や血管の異常等が考えられるが,もともとCは高血圧や妊娠高血圧症候群等ではないので,その可能性が高いとはいえず,他方,脳出血を発症した妊婦の半数はなんら危険因子を持たない(乙B26の2)ことからすると,結局,原因は不明であるというほかない。
4 争点2(頭部CT検査を実施せず,転送が遅延した過失)
原告らは,Cが午前零時14分ころ意識を消失し,そのまま意識が回復しなかったのであるから,脳内病変を疑って頭部CT検査などを実施すべきであったのに,その義務を怠り,脳出血の診断が遅れ,脳圧下降剤の投与もされなかったと主張する。
(1)まず,Cが午前零時14分ころに意識を消失した後に被告D医師らがCT検査を実施しなかったことが過失にあたるかについて検討する。
ア Cは午前零時ころに脳出血が始まったと考えられるので,午前零時14分ころに頭部CT検査あるいはMRI検査等を実施していれば,何らかの所見が得られた可能性は高いと考えられる。しかし,こうした検査は,患者の負担等を考えると,何らかの疾患を疑った場合に実施するものであるところ,この時点では,Cは意識消失はあるが,血圧は147/73,脈拍は73回/分, は97%SpO2 であり,顔色は正常であったなど,全身状態に問題はなかったのであるから,被告D医師らにおいて経過観察でよいと判断したことが不適切であったということはできない。
もっとも,精神的な反応から来る心因的意識喪失発作であれば意識喪失は30分程度で回復するものである(E医師も30分前後で治まるものであると証言している。E医師証人尋問調書24頁)ところ,その後も30分以上意識障害が継続していることは脳に何らかの異常が生じていることをうかがわせるということができる(M鑑定も,CT検査をしなかったことが不適切であるとはいえないとしながらも,午前零時30分ころの診察後脳の障害を疑いCT検査を実施するチャンスはあったと考えられる旨述べる。)。
そして,午前1時37分ころには,血圧が自動血圧計で175/89,水銀血圧計で200/100となり,除脳硬直が生じているのであるから,Cの脳に何らかの異常が生じており,そのことは容易に診断できたということができる。現に,E医師はCT検査の実施を被告D医師に尋ねており,被告D医師も,子癇と考えつつも脳の異常が生じている可能性については認識していたものと考えられる。
イ 問題となるのは,原告らが主張するように,頭部CT検査をしなかったために,脳出血の診断が遅れ,脳圧下降剤を投与する機会を逸したことをもって過失といえるかという点である。
確かに,午前1時37分ころには脳に何らかの異常が生じていることを認識することは可能であり,現に被告D医師らにおいて認識していたと考えられるのであるから,通常直ちにCT検査を実施すべきであったといえる。しかし,被告D医師において,午前1時37分ころの時点で,一刻を争う事態と判断し,CT検査に要する時間を考慮すると,高次医療機関にできるだけ迅速に搬送することを優先させ,直ちに奈良県立医大に対し受入れの依頼をしているところであって,頭部CT検査を実施せずに搬送先を依頼したことが不適切であったといえるものではない。
もっとも,結果的には,午前1時50分ころに奈良県立医大に対し受入れの依頼をし,国立循環器病センターへの搬送が開始されたのは午前4時49分であるから,約3時間を要しているところ,被告病院においてCT検査は40~50分程度で実施可能であることからすると,CT検査を行うことができたということができ,それにより脳に関する異常を発見してグレノール(脳圧下降剤)の投与等の措置をとることができた可能性は否定できない(ただし,本件ほどの血腫の場合,脳圧下降剤の効果があるかは疑問視される(K証言・証人尋問調書17頁)。)。しかし,被告D医師のそれまでの経験では搬送先が決まるまで長くても1時間程度であったことからすると,CT検査を実施すると,その実施中に搬送先が決まる可能性が高く,その場合には,CT検査の実施が早期の搬送の妨げとなることも考えられるところであって,CT検査を実施するよりも早期に搬送することを選択した被告D医師の判断は,十分な合理性を有しているということができる。そして,CT検査は極めて有用ではあるが,検査に出室させることによるリスクや検査中不測の事態をも考慮し施行時期を慎重に選択することが重要であるとされているところであって,まず受入れを依頼し,搬送先の病院に検査をゆだねた被告D医師の判断が不適切であったということはできない。
N意見やO意見は,被告病院においてCT検査を実施すべきであったとするが,上記の理由により採用できない。
(2) 原告らは,Cが8日午前零時14分ころに意識を消失してから数分経過した時点で頭部CT検査を実施していれば,午前1時までには脳出血の存在が明らかになっており,脳外科救急機関は数多くあることから,搬送先を確保することは困難ではなく,より早期に治療を受けることができたとして,転送を遅延させた過失を主張し,N意見も同旨を述べる。
しかしながら,CT検査を実施し,脳出血であるとの診断ができたとしても,現に分娩進行中であるから,産婦人科医の緊急措置が必須であることに変わりはなく,子癇の疑いとして搬送先を探した場合に比べて受入施設の決定がより容易であったとはいいがたい。仮に,原告Aにおいて,脳外科の医療機関を希望したとしても,現に分娩が進行中であり,脳外科医が分娩を放置してCの脳出血の治療のみに専念するとは考えがたく,脳外科と産婦人科の双方の対応が可能な医療機関に転送することがやはり必要であり,CT検査を実施し,脳出血であるとの診断がついていたとしても,早期に搬送先の病院が決まったということはできない。
(3)以上のとおり,被告D医師らにおいてCT検査を実施せず,転送が遅れた過失を認めることはできない。
5 争点3(因果関係)
以上のとおり,被告D医師らに過失を認めることはできないが,因果関係も争点となっているので,この点についても判断することとする。
(1)本件において,被告D医師らにおいて,最も適切な措置を講じることができたことを前提として因果関係について検討する。
前記のとおり,午前零時14分ころの時点では脳出血が生じていると診断することは無理であって,経過観察としたことは相当であった。しかし,心因的意識喪失であれば意識喪失が30分以上継続することは通常ないのであるから,午前零時14分ころから30分が経過した時点で,改めて診察をし,脳に何らかの異常が生じていることを診断し,直ちに搬送先を探し始めるというのが,被告病院が取り得た最善の措置であったということができる。仮に,午前零時14分ころから30分余が経過した午前零時50分の時点で搬送先を探していたとすると,これからは全く仮定の話になるが,被告D医師は奈良県立医大に依頼したと考えられ,その時点であれば,奈良県立医大においてたまたま受入れが可能であったとする。その場合,直ちに搬送手続を開始したとしても,搬送に30分程度は要することになり,救急車の出動要請もあるので,奈良県立医大への到着は午前1時30分ころになったと考えられる。そして,人的物的設備が整った国立循環器病センターにおいても,産科医,脳神経外科医,麻酔医らを集め,準備をすすめても,手術を開始するまでに,約2時間(午前5時57分に搬送され,血腫除去術開始は午前7時55分)を要しているのであり,その程度は奈良県立医大においても必要であったと考えられる。そうすると,奈良県立医大での手術開始は午前3時30分ころになったと考えられる。
ところが,前記認定のとおり,午前2時ころには,瞳孔が散大し,呼吸が26回/分と過換気の状態となり,呼吸障害も起こり,「中脳-上部橋期」に相当し,通常非可逆的である。Cの病態の進行は急激であって,午前2時ころから数十分以内に開頭手術を行わないと救命は不可能であったのであるから,午前3時30分ころの時点で緊急の開頭血腫除去術を行っていたとしても,救命の可能性は極めて低かったと考えられる。したがって,午前零時ころに脳出血を発症し進行が急激であったCの病態からすると,被告D医師らにおいて想定しうる最善の方策を講じたとしても,救命することはできなかったということができ,救命できた相当程度の可能性も認めることはできない(仮に,被告病院においてCT検査を実施し,脳出血の診断を得て,その旨搬送先に連絡し,搬送先において予め脳神経外科医による手術準備をしていれば,搬送先病院における受入れから手術までの時間は短縮できるが,逆に被告病院におけるCT検査の時間を要し,全体として短縮にはならない。)。
逆に,時系列をさかのぼって検討してみる。前記のとおり,遅くとも午前2時ころから数十分以内には開頭手術(血腫除去術)をする必要があり,その時刻を午前2時30分としてみると,前記の経過からすると,電話で受入れの依頼をしてから搬送,診断,手術準備までに2時間40分程度(奈良県立医大への搬送までに40分,手術開始までに2時間程度)を要することからすると,7日午後11時50分ころまでに受入依頼をする必要があったといえるが,その時点ではいまだ脳の疾患を疑わせるような所見はなく(疑わせる最初の症状は午前零時ころの頭痛である。),Cを救命することはできなかったということができる。
(2)以上に対し,原告らは,午前2時あるいは3時の時点でも痛み刺激に対する反応があり,JSC200,瞳孔4~5㎜で中等度固定,呼吸正常であり,午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば,十分に救命できたと考えられると主張し,N意見も同旨を述べる。
しかしながら,前記のとおり,午前1時37分ころに除脳硬直が生じていることは,脳出血が中脳から橋に及んでいることを示しており,午前2時ころには瞳孔が散大となっているのであるから,Cの脳損傷は致命的であって,午前4時ころまで救命できたということはできない。
6 結論
以上のとおり,被告D医師らにCT検査を実施しなかったことについて過失を認めることはできず,仮に過失を認めたとしても,Cが死亡したこととの間に相当因果関係があるということもできない。結局,本件においては,Cに脳出血があってからの経過が急激であるため,産婦人科,脳神経外科,麻酔科が完備した病院で分娩をし,緊急の対応が可能であった場合でない限り救命できなかった,あるいはその条件が揃っていたとしても,救命できたかわからない事案であったということができる。
したがって,原告らの各請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
よって,原告らの各請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
7 当裁判所の付言
以上のとおりであるが,本件は18件もの病院に受入れを拒否されたとして大きく報道された事件である。原告Aや家族らは,Cについて,午前1時37分ころのけいれん発作により転送が決められてから実際に救急車が被告病院を出た午前4時49分までの間,意識を喪失したまま脳に異常が生じているにもかかわらず,脳に対する検査や治療がされることなく搬送先が決まるのをひたすら待っていた。もっと早期に搬送されていれば救命されたのではないかという原告Aらの気持ちは十二分に理解できる。1分でも1秒でも早く治療をしてもらいたいのに,何もすることなく,3時間待たされ続けたわけである。その待っていた時間がいかに長いものであっただろうか-。
本件以後においても,同じ奈良県で平成19年8月に切迫流産の妊婦が搬入先が決まらずに流産したケースや,平成20年10月に東京都内において脳出血の疑いがあるため手術可能な病院に転送しようとしてなかなか決まらずに妊婦が死亡したケースなどが報道されている。
最後に,当裁判所として,産科を始めとする救急医療について付言しておきたい。
(1)消防庁が平成21年3月に発表した「平成20年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果」(乙B39)によると,平成20年期救急搬送の受入状況は,次のとおりである。
産科・周産期傷病者搬送事案は,全国で4万0542人であり,このうち搬送依頼の照会回数が4回以上のもの749件(全体の4.6%),6回以上のもの265件(同1.6%),11回以上のもの47件(同0.3%)であり,最大照会回数は26回であった。現場滞在時間区分では,搬送先が決まらずに救急車等が現場に30分以上滞在したもの1029件(全体の6.3%),45分以上のもの311件(同1.9%),60分以上のもの113件(同0.7%)となっている。産科・周産期傷病者搬送事案に限定せずに,重症以上傷病者搬送事案についてみると,搬送者は全国で41万2836人であり,照会回数が4回以上のもの1万4732件(全体の3.6%),6回以上のもの5138件(同1.3%),11回以上のもの903件(同0.2%)であり,最大照会件数は49回であった。現場滞在時間区分では,現場滞在時間が30分以上のもの1万6980件(全体の4.1%),45分以上のもの4440件(同1.1%),60分以上のもの1663件(同0.4%)である。こうした選定困難事案の割合が高いのは,首都圏や近畿圏等の大都市に集中しており,近畿圏内では,大阪府,兵庫県,奈良県が該当する。
1分でも1秒でも早く病院に搬送され,早期に必要な措置を受ける必要がある重症患者について,現場滞在時間が30分以上というのが1万6980件(4.1%)もあってよいものであろうか。これでは「救急医療」とは名ばかりである。
もちろん,本件のように,たまたま各病院とも満床等により受け入れることができないというのは珍しいことであろうし,救急医療体制を充実させても,患者が来ないために空きベッドが多く,経済的な観点から相当でないという背景があるのかもしれない。しかし,人の命は最も基本的な根源をなす保護の対象であり,それを守ることは国や地方公共団体に課された義務であって,経済的効率性の観点から判断してよいものとは思われない。人の命の大切さをもう一度考えることが必要である。
本件が生じたことを受けて,国立循環器病センターのJ医師らは,妊娠に合併した脳卒中などの成人一般救急疾患の診療体制について調査を実施し公表している(平成19年3月,乙B25の4)。その報告は,救急に対応するために周産期母子医療センターは妊産婦や新生児の「最後のとりで」とされているが,全国にある41の総合周産期母子医療センター(大学附属病院を除く)のうち,約4分の1で,成人一般救急疾患の診療体制が不十分であり,未熟児・新生児医療を主眼に発展してきたわが国の周産期医療のピットホールと呼ぶべき現象であり,近隣の大学や救命救急センターなどとのネットワークを考慮した周産期医療の再構築の必要性を述べている。また,大野泰正「妊娠高血圧症候群から子癇発症に至る機序解明と診断管理法確立へのアプローチ」(日本産科婦人科学会雑誌60 巻9 号,平20)は,妊婦に対する救命措置を最優先し,可能な状況であれば緊急CTによる脳出血の除外診断を行うこと,脳出血を認めた場合は即座に脳外科対応可能な高次施設へ搬送すること,日頃より搬送先の高次医療施設の受入状況を把握しておくことを強調している。さらに,最近,傷病者の症状等に応じた搬送及び受入れの円滑化を図るため消防法の一部改正がされたほか,厚生労働省から平成21年3月に「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する報告書~周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて~」が発表され,母体搬送体制の整備等の必要性が述べられている。このように本件が発生したことも理由の一つとして,産科の救急体制の整備が進められている。
しかし,他方において,現在,救急患者の増加にもかかわらず,救急医療を提供する体制は,病院の廃院,診療科の閉鎖,勤務医の不足や過重労働などにより極めて不十分な状況にあるともいわれている。医療機関側にあっては,救急医療は医療訴訟のリスクが高く,病院経営上の医療収益面からみてもメリットはない等の状況がこれに拍車をかけているようであり,救急医療は崩壊の危機にあると評されている。
社会の最も基本的なセイフティネットである救急医療の整備・確保は,国や地方自治体の最も基本的な責務であると信じる。重症患者をいつまでも受入医療機関が決まらずに放置するのではなく,とにかくどこかの医療機関が引き受けるような体制作りがぜひ必要である。救急医療や周産期医療の再生を強く期待したい。
(2) 本件で忘れてはならない問題がもう一つある。いわゆる1人医長の問題である。被告病院には常勤の産科医は被告D医師のみであり,出産時の緊急事態には被告D医師のみが対処していた。1人医長の施設では連日当直を強いられるという過重労働が指摘されている。本件で,被告D医師は夜を徹して転送の手続を行い,救急車に同乗して国立循環器病センターまで行った後,すぐに被告病院に戻り,午前中の診察にあたっている。平成20年に日本産科婦人科学会が実施した調査では,当直体制をとっている産婦人科の勤務医は月間平均で295時間在院している。こうした医療体制をそのままにすることは,勤務医の立場からはもちろんのこと,過労な状態になった医師が提供する医療を受けることになる患者の立場からしても許されないことである。近時,このような状況改善の目的もあって,医師数が増加されることになったが,新たな医学生が臨床現場で活躍するまでにはまだ相当な年月を要するところであり,それまでにも必要な措置を講じる必要があるものと思う。
近年女性の結婚年齢や出産年齢が上がり,相対的に出産の危険性が高まることになる。より安心して出産できる社会が実現するような体制作りが求められている。
(3) 愛妻を失った原告Aの悲しみはどこまでも深い。Cは我が子を抱くことも見ることもなくこの世を去った。原告Bは生まれた時から母親がいない悲しみを背負っている。Cの死を無駄にしないためにも,産科等の救急医療体制が充実し,1人でも多くの人の命が助けられることを切に望む。
大阪地方裁判所第17民事部
裁判長裁判官 大島眞一
裁判官 和田三貴子
裁判官 青野初恵
【参考ブログ】
「マスコミたらい回し」とは?(その157)大淀病院産婦死亡事例民事裁判判決文を読む
天漢日乗 2010-03-19
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2010/03/157-65ee.html
最近のコメント