(関連目次)→医療訴訟の現状 目次 萎縮医療 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
こんな連載をしていらっしゃったとは知りませんでしたo(^-^)o ..。*♡
M3です。とってもためになるかどうかというと。。。。
もう入っちゃってるからわかんない。(←テキトー)
でもせっかくです(>▽<)!!!!
3回企画&その後の質問を上げさせていただきます!!
なぜ勤務医に「医師賠」が必要か
勤務医・研修医個人が訴えられるケースも
高月清司(IMK高月(株)代表取締役)
m3.com 2008年10月16日
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/081016_1.html
ここ数年、医療事故や訴訟関連のニュースが日常的に報道されるようになっている。こうした医療訴訟などに対するリスクをヘッジするのが「医師賠償責任保険(以下、医師賠)」である。これは病院などの勤務医や開業医が加入する保険だが、勤務医の加入率はまだ高くはない。私自身も関係している、メディカルリスクマネジメント情報連絡協議会の推定では、2004年度の卒後臨床研修制度の必修化以降、研修医に加入を義務付ける医療機関が増えたこともあって、20-30代の医師では60-70%が医師賠に加入しているもようだが、40-50代の加入率は50%を割っていると言われている。
従来は医療事故に対する賠償金などの補償は病院が負担してきた。しかし、後述のように病院が医師の責任分まで賠償金を支払えない時代に入っており、自らを守る手段として勤務医の医師賠への加入価値は高い。
一方、開業医が日本医師会に加入した場合は強制的に医師賠(日本医師会の賠償責任保険)に加入しているので問題はないが、“医師会離れ”が進んでいるとされる中、開業したら開業の形態に合わせた医師賠に加入する必要がある。また、開業して法人化したり、連携する地域の病院に出向いて診療・治療を行う場合、そこで起きた医療事故には自分の医師賠が使えないケースも出てくるので、業務の実態に合わせて勤務医用の医師賠と重ねて加入するようにしたい。
1.訴訟件数の増加と賠償金額の高額化
現在、医療訴訟で新規に提訴される件数は年間1000件前後。ここ数年はほぼ横ばいだが、それでも依然として高い水準にある。また、裁判所が抱える医療訴訟(民事)の係争件数は全体で約3000件とされている。弁護士数が急増している現状から、今後、訴訟件数はさらに増えるとの予測もある。
診療科別では、従来から外科・整形外科、内科、産婦人科の3部門での訴訟が多かったが、今では診療科に“聖域”はなくなった。例えば、今まで訴訟リスクは低いと考えられていた精神科などでも、うつ病で治療中に発作的に自殺してしまった患者の家族が治療ミスを訴え出るなどのケースで訴訟が増加している。
精神科医が一番心配するのが、診療中の患者が起こした事件が元で、自分の診察ミスとして責任を追及されるケースだろう(例:2000年の西鉄バスジャック事件では、精神科に入院中の少年が許可を得て外出中に殺人事件を起こしたため、この病院に対して批判が集中した)。しかし、日本の判例では賠償責任は直接責任に限定されるケースが多く、今のところ、こうした事例で精神科医の責任が認定されるまでに至っていない。
賠償金額の高額化傾向も続いている。その算出の基礎となる平均余命(可働年数)や所得金額が増えるに従い、さらに高額化していくものとみられている。例えば、2005年2月、福岡地裁で、陣痛促進剤の過剰投与が元で脳性麻痺が残ったとして、9歳の男児の両親が介護費用なども併せて2億6000万円の賠償請求を求めて提訴している。10年前ほど前までは1憶円を超える賠償請求は稀であったが、最近では2億円を超える賠償請求は珍しくなくなった。
また、最近の訴訟で特徴的なのは、患者側の損賠賠償の請求金額に近い金額で判決が出るケースが増えている点だ。判決は世論に流される傾向が見られるが、患者=弱者救済の流れから、世間一般に“リッチ層”と思われている医師にとって逆風は当分続くかもしれない。
2.研修医個人も訴えられ、8400万円賠償金請求
10年ほど前までは、患者側は医療機関を相手取って提訴していた。つまり訴状では「被告:A病院」となっていた。しかし、最近は関係した医師やコメディカルの名前を被告名に連記し、「被告:A病院、B医師」とされ、「連帯して支払え」と訴えるケースがほとんどだ。研修医についても例外ではなく、卒後臨床研修の必修化に伴い、身分と報酬が確立されたことを背景に、ハッキリと責任を課す判決も増えている。
例えば、2005年1月の埼玉高裁の判決では、抗癌剤の過剰投与で患者が死亡した事件で、病院に加えて、実際に過剰投与した研修医の責任も認め、計8400万円の損害賠償の支払いを求めている。さらに、最近では、勤務医であっても医師個人が訴えられるケースも出ている。
3.病院賠と医師賠の違いが影響
個人の医師が加入する医師賠のほかに、病院が加入する「病院賠償責任保険(以下、病院賠)」がある。これは勤務医個人が加入する医師賠に、医療施設としての管理責任をカバーするもので、病院賠の補償内容は個人の医師賠と相違はない。
異なるのは保険料の仕組みだ。勤務医が加入する医師賠は個人が何度保険を使っても翌年度以降の保険料は今のところ変わらないが、この病院賠は自動車保険と同様、医療事故を起こし保険金の支払いを受けた場合、次年度以降の保険料に大きく影響する仕組みとなっている。従って、全国の病院の7-8割が赤字経営に苦しむとされる中、個人医師に医師賠加入を義務付け、なるべく保険料に増減のない医師賠の保険から保険金支払いを受けようとする病院が増えるのは、経営上無理からぬことと言える。
「医師賠」の基礎知識と賢い選択法
補償内容に4つの特徴、取り扱い会社は5社
高月清司(IMK高月(株)代表取締役)
m3.com 2008年10月23日
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/081023_1.html
1.医師賠を扱う保険会社は5つ
医師賠を扱っている保険会社は、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上、日本興亜損保の4社で、最近AIG系のアリコジャパンが始めたので、計5社に限られる。
2.補償内容の4つの特徴
医師賠は、医師本人の医療行為に起因する医療事故を補償する。保険会社で補償内容に大差はなく、以下の4つの特徴がある。
(1)日本国内で行われた医療行為に限る
(診療所開業医の場合、そこに勤務する医師の医療行為、
医師の指示を受けた看護師をはじめとするコメディカルの
医療行為も含まれる)
(2)対人賠償のみ(対物賠償は、別の医療施設賠償責任保険でカバー)
(3)法律上の賠償事故に限る(保険会社へ未通知のまま示談したり、
医療側の過失責任が認められない行為は対象外。
なお、民事裁判において過失が認められなかった場合でも、
弁護士費用など、かかった費用は対象となる)
(4)医療側が医療事故を認識(発見)した日が、保険期間内(通常は1年)
であること(事故発見日ベース)。ただし、扱い5社のうち、
損保ジャパン社だけは、患者側が賠償請求した日が保険期間内
であること(賠償請求ベース)。
3.補償内容
医師賠、特に勤務医向けの補償内容は、特約がたくさん並ぶ自動車保険などと比較すると、特約も免責もなくシンプルだ。一方、自動車保険にあるような示談交渉代行サービスは付いていない(=病院が窓口になって交渉する)が、弁護士費用なども補償に含まれるので、対象と決まれば訴訟費用などにかかる金銭的負担はほとんどないといってよい。
加入できるタイプは次の2つに代表される。
(1)一般的なタイプ:1事故・1億円/期間中(通常1年)・3億円
(2)最大補償タイプ:1事故・2億円/期間中(通常1年)・6億円
「期間中」が付いている意味は、医療事故は「いつ・どこで・誰が起こした」などが即座に判明できないためだ。原因となった過去の手術について(事故日)、患者側が数年経ってから訴えてくるケースが多い。ある医師のケースでは、7年前の事故と昨年の事故の2例が、同じ年に訴訟になったこともあり、過去の事故が提訴された場合にも対応できるよう、「期間中」が付けられている。
4.保険料
病院賠の保険料は、病床規模のほか、事故の多少やリスク管理への取り組み姿勢などに応じて病院別に設定される。一方、医師賠の保険料は、医師個人による差はなく、かつ保険会社による相違もない。補償内容の違いで2つのタイプが普及している。(どちらも掛捨てタイプ)
(1)一般的なタイプ:50,830円(20%の割引が効けば、40,660円)/年
(2)最大補償タイプ:66,030円(20%の割引が効けば、52,820円)/年
日本の保険料は世界的に見ても大変安い。米国では診療科により異なるが、脳神経外科では年間1000万円を超えるものすらあるという。これは賠償金が高額化しているためで、保険料を払える医師も少ないため、保険会社はビジネスとして成り立たなくなりつつあり、撤退する保険会社もある。日本でも同様にこのまま訴訟件数や高額賠償事案が続くと、個人医師向けの医師賠も含めた保険料のアップや、保険会社の撤退も起こり得ると懸念されている。
5.加入経路
勤務医師が個人単独で加入するケースはほとんどなく、大概は何らかの団体経由で加入している。団体経由のメリットは、加入人数により保険料割引が最大20%まで効くからだ。
主だった団体を大別すると次のようになる。
(1)医師会系:開業医中心。勤務医師も加入できるが、100万円の免責がある。
(2)学会系:外科学会などのほか、コメディカルでは各協会が募集。
(3)同窓会系:医学部の同窓会が募集。
(4)任意団体:病院や医局単位、または研究グループなど。
加入時と加入後、どんな点に注意すべきか
勤務先の変更や留学時には要注意、「過失割合」確認も重要
高月清司(IMK高月(株)代表取締役)
m3.com 2008年10月30日
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/081030_1.html
1.加入時の注意点
団体経由では割引保険料が得られるメリットがある一方で、加入時にVol.2(『「医師賠」の基礎知識と賢い選択法』を参照)で解説したような詳しい説明を受けられないケースも多い。疑問な点があったら、必ず加入団体または保険に詳しい取扱代理店に確認しておくようにしたい。また保険加入期間であっても、途中で加入団体を脱退した場合などでは、会員資格がないと補償の対象とならない場合もある。このような場合に、自分の保険が引続き有効かも併せて確認しておく必要がある。
さらに、留学中は臨床に携われないからと、いったん保険を解約してしまうケースも多いが、Vol.2で解説した「事故発見日ベース」の兼ね合いから、解約している間に留学前の診療が原因で訴えられると保険が効かないので、留学中も保険は継続しておくべきだ。
2.加入後(事故処理上)の注意点
患者から何らかのアクションがあって初めて医療事故を認識するケースも少なくないが、その場合、必ず保険会社への通知が必要だ。勝手に示談金を支払った後に保険金を請求しても、保険金が下りないケースもある。また、いったん事故が発見されると病院が窓口になって対応することになる。具体的には、病院側(院長や事務責任者、および担当医)のほか、顧問弁護士や保険会社が対応を協議し、患者側との応対に当たる。
その顧問弁護士や保険会社から証拠の保全や事故の詳細について質問があるが、勤務時間を調整するなどしてできるだけ協力するようにしたい。弁護士からは「委任状」への捺印も要請されるが、弁護士費用などの請求に必要な書類なので、応じて構わない。
同時に、自分が加入している団体や取扱代理店を通して、自分サイドの保険会社にも事故の概略(5W1H)や病院側の対応経緯も簡単に箇条書きで良いので通知しておきたい。通知はなるべくメールにしたい。代理店や団体が返してきた返事も記録に残るので、のちのち助かることが多い。
示談や訴訟が進む段階で、自分の過失や病院側の管理責任について疑問が生じることがある。このような場合、勤務先との無用なトラブルも避けたい気持ちが働く一方で、自分の主張が認められないストレスもあり、余計な悩みを抱えることも多いのが現実だ。こうした時も、遠慮なく団体や取扱代理店に相談するとよい。過去の判例などを基に適切なアドバイスも得られやすく、中には無償で顧問弁護士などからセカンドオピニオンを聞いてくれるところもあるので、事故を抱えた勤務医には大きな助けとなり、以降の交渉にも好影響が期待できる。保険を選ぶ際は、この辺りも対応してもらえるか、確認することも必要だろう。
3.病院と勤務医の「過失割合」に要注意
また、一般的にはあまり知られていないが、事故処理後、勤務医にとってはまだ大変重要な確認事項が残っている。それは「過失割合」の確認だ。判決などでは、「医療側は連帯して1億円支払え」という大枠しか述べられないため、その後、病院側と勤務医側で、過失割合に沿って負担額が決められる。具体的には、病院(管理責任)側と医師(治療行為)側とでどれだけの割合で過失があったかを、過去の実績から保険会社と、病院と勤務医、双方の弁護士が査定を行う。その査定の過程で勤務医個人に相談があることは少ないのが実情なので、この過失割合(分担割合と言うこともある)を病院の事務局からしっかり確認し、不明な点があるなら加入団体や保険に詳しい取扱代理店に確認しておくとよい。 ケースによって相違はあるが、過失割合は病院80:医師20というのが一般的だ。ところが、高額賠償ケース=病院賠を使うと次年度の保険料に影響するケースでは、病院50:医師50とする場合が結構ある。しかし、その事案をよく検証すると、病院80:医師20にしてもおかしくないケースも多くあるので、確認が必要だ。
医師個人の過失割合は、米国などへの臨床留学や国内の転職において医師を評価する大変重要なポイントとなっている。研究目的の留学では問題ないが、臨床に携わる場合、留学先が日本の保険会社や代理店に事故歴を照会するケースがある。米国ではこの点に厳しく、米国のマサチューセッツ州では医師免許の更新のたびに、「過去10年の事故履歴と過失割合」を聞いてくるくらいだ。
しかし、この過失割合は重要であるにもかかわらず、査定作業をきちんと専門的に行っている団体(あるいは代理店)は、日本医師会を除くと、ごく一部の専門代理店のみでその数は大変少ないのが現状だ。ほとんど保険会社任せの状態のため、勤務医にとっては大変危険な状況と言える。交渉上不利と感じた場合は、加入する団体や代理店、あるいはそれらを通じて、弁護士に相談すべきだろう。
4.新しい取り組みー訴訟防止に向けてー
一方、訴訟とは違う新しい動きも始まっている。それは、ADRや医療版メディエーターという、米国では一般的になりつつある新しい紛争解決方法だ。
米国では1980年代に医療訴訟が激増し、賠償金額も超高額化した(数十億円、数百億円の請求が話題になった)ため、ビジネスとして機能しなくなった保険会社の多くがこの医師賠から撤退し始めてしまった。その結果、医師や医療機関は支払いリスクを抱えたまま患者を選択診療(リスクの高い診療をしないなど)を行ったり、あるいは医師が廃業して医療機関がどんどん閉鎖に追い込まれていき、結局、患者が不幸な状況に追い込まれる現象が生まれてしまったのである。
国民皆保険の日本とは条件や背景が違うにせよ、日本でも医師不足や相次ぐ病院や診療科の閉鎖は、こうした医療訴訟リスクも1つの原因だと言われている。日本の保険会社においても、「赤字状態」とされる医師賠の保険料の大幅値上げや医療機関の選択(訴訟リスクの少ない病院しか加入できなくなる)などが早晩行われるかもしれないと懸念されている。
米国におけるこの瀕死の状態を救ったのが、中立的ADRだとされている。「示談と訴訟の間の中立的話し合い制度」と考えれば分かりやすい。つまり、現在では医療側と患者側による示談で話し合いが付かない場合、残る手段は訴訟しかないが、法廷論争では一般に過失の有無や不法行為のみに論点が集中せざるを得ないため、当事者同士の話し合いはもちろん、患者側が本当に知りたい死因を知ることも、医療側による主張や謝罪の機会も失われてしまう弊害がある。
この示談と訴訟の中間の制度として存在するのがADRで、医療・患者間の中立的立場として専門資格を取得した医療メディエーターなどを介在させることで、踏み込んだ話し合いと事後のフォローをよりきめ細かに実現できると言われる。
既に日本医療メディエーター協会などでは、院内メディエーターの養成などを行っている。近畿圏にある大規模病院ではADRの活用で実際に訴訟が減少し、同時に保険料も減少に転じたという報告もなされている。また、一部の弁護士会でも、こうしたADRの動きを取り入れているところも出始めている。さらに、結果として支払う賠償金が減れば保険会社にとってもメリットが生まれるため、まさに患者、医療者、保険者の「3方1両得」の制度と注目されている。
判決が弱者(=患者)サイドに流れ、賠償金額が高額化する傾向が多くみられる中、こうしたADRなどの新紛争解決手段に期待する一方で、「自分の身は自分で守る」をキーワードに、医師個人も必ず医療リスクへの対策を講じておきたい。
皆様の質問にお答えします、「医師賠」について
m3.com 橋本編集長 2008/11/07
http://mrkun.m3.com/DRRouterServlet?pageFrom=CONCIERGE&operation=showMessageInDetail&pageContext=CONCIERGE&msgId=200811071811768908&mrId=ADM0000000&onSubmitTimeStamp=1226049864687&onLoadTimeStamp=1226049862921
先月、「勤務医のための医師賠償責任保険(医師賠)入門」を3回に分けて連載しました。病医院だけではなく、医師個人が患者側から訴えられるケースがあり、個人で賠償責任保険に加入する必要性が高まっているものの、まだ加入率はまだ高くはないのが現状です。そこで企画したのが今回の連載です。
m3.comの会員の皆様から、幾つか質問をいただきましたので、執筆者の高月清司氏(IMK高月(株)代表取締役)に回答をお願いしました。
◆質問1: 歯科医師、薬剤師、看護師などの職種にも、個人加入できる賠償責任保険はあるか?
回答1:
ある。歯科医師、薬剤師、看護師、作業療法士にはそれぞれの賠償責任保険が存在する。歯科医師の場合は、医師と同じく、学会や各地区の歯科医師会でも扱っている。薬剤師や看護師などについても、日本薬剤師会や日本看護協会などが扱っているが、補償内容は医師賠のように各保険会社同一ではなく、少しずつバリエーションがあるようなので、他の職種の方も含めて各協会窓口に相談するとよい。
医師以外にも賠償責任保険が普及したのは、看護師による患者取り違え事件などがきっかけ。しかし、一時の加入ブームが去ったとはいえ、訴訟リスクは依然としてあるので、加入しておいた方が万全だ。
◆質問2:A病院の常勤医Bが、C病院にアルバイトに行った。そこで行った診療がもとで、患者に障害が残った。常勤医Bは医師賠に加入しているが、補償金は下りるか?
回答2:
補償可能。第2回『 「医師賠」の基礎知識と賢い選択法』で、「2.補償内容の4つの特徴」の(1)に記載した通りで、日本国内における医療行為であれば、その行為を行った医療機関にかかわらず、カバーされる。
◆質問3:A病院の常勤医Bが、A病院で医療事故を起こした。患者側は常勤医B個人を相手に提訴。この場合、A病院が病院として加入している保険から補償金を出すことは可能か。
回答3:
補償は可能。提訴や示談が医師個人のみを相手取ったケースであっても、初期対応は病院窓口で行う。これは後に病院の管理責任が問われるケースに備えての対応で、保険約款上も病院経由で医師個人の賠償責任として支払うことが可能。
ただし、第1回『なぜ勤務医に「医師賠」が必要か』で記したように、「病院賠」は補償金の支払いが次年度以降の保険料に影響するため、全く病院としての責任がないと判断されたケースでは、医師個人の了解を得て、医師個人が加入する保険から支払うという方法が一般的になりつつある。
◆質問4:A病院の常勤医Bが、C病院を受診していた患者から癌の診断についてのセカンドオピニオンを受け、癌はないと診断した。しかし、1年後、癌の転移が原因で死亡。C病院とともに、常勤医Bも訴えられた。仮に常勤医Bの過失が認められた場合、補償金は下りるか。
回答4:
下りる。セカンドオピニオンの診断ミスが原因で、患者に身体障害(死亡)を来したケースに当たる。もっとも、見落としは過失認定が大変難しく、PETなど精密な診察を行わないセカンドオピニオン時の診断ミスは過失とは言えない、とする判決もある。
(最近、セカンドオピニオン、特に癌の見落としに関する相談や訴えも結構多く、セカンドオピニオンに対応する医師が少なくなるのではないかと懸念している。セカンドオピニオンを行うに当たっては情報が必ずしも十分でない場合もあり、かといって諸検査を一から行うことについては患者も嫌がるため、難しさがある。同様に、十分な診療環境下にない往診時の診断ミスなどを恐れ、往診する医師が減少しているとも聞くが、こうしたリスクを反映していると思える)。
高月 清司(こうづき きよし)氏
医業経営コンサルタント。1977年慶應義塾大学商学部卒。国内や海外において会社勤めの後、東京海上勤務を経て医師賠償責任保険を専門とした代理店・IMK高月(株)を設立して独立。現在、日本医業経営コンサルタント協会認定の医業経営コンサルタントとして、病院や勤務医向けの医療訴訟防止に向けて活動中。

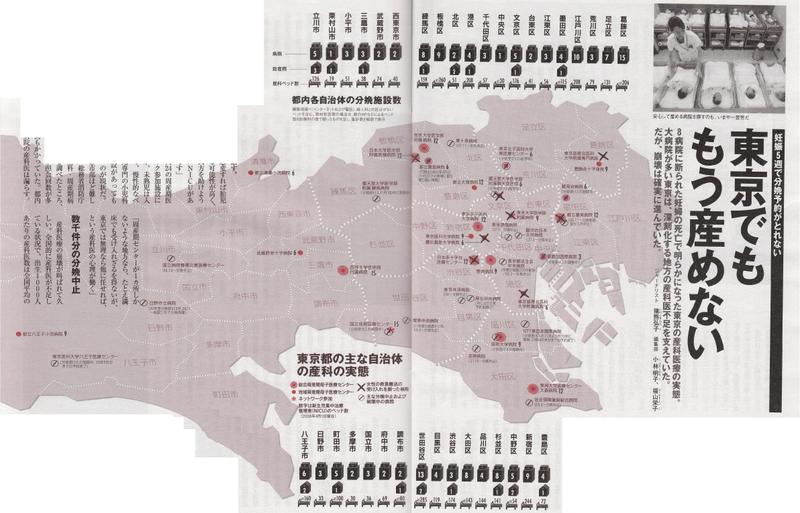
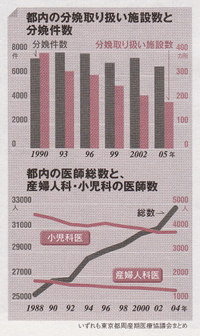




最近のコメント