(関連目次)→大野事件 医療事故と刑事処分 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
 法律時報2008年11月号 1002号よりo(^-^)o ..。*♡
法律時報2008年11月号 1002号よりo(^-^)o ..。*♡
特集は 新たな労働者保護のかたち です!
でも今回とりあげるのは大野事件!
なんだか難しいけれど、頑張ってお読みくださいませ♪
医療水準と医療の裁量性
―福島県立大野病院事件・福島地裁判決を中心に―
小林公夫
(法律時報80巻12号 p70-75)
一 福島県立大野病院判決と“医療水準”論
二〇〇四年一二月一七日福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性(当時二九歳)が死亡した医療事故で、福島地裁は、二〇〇八年八月二〇日、業務上過失致死と医師法違反に問われた医師に無罪(求刑禁錮一年、罰金一〇万円)を言い渡した。
本件においては公判の過程で、死亡した女性の帝王切開手術により女児が生まれた後、被告医師がとった行為の是非が争点となった。大量出血後も癒着胎盤の剥離を継続し、剥離を中断し子宮摘出手術に移行しなかった医師の行為が、医の準則に合致したものか否かが問われたのである。そして、胎盤剥離を中止し、子宮摘出手術に移行し、剥離に伴う大量出血による生命の危険を回避すべき注意義務が被告医師にあったとする検察側主張に対し、弁護側の主張が真向から対峙する形をとった。
すなわち、癒着胎盤は一万分娩に二~三回発生するかどうかというごくまれな疾患であり、産科医が一生のうちに一例か二例遭遇するかしないかの疾患であること、また、癒着胎盤の事前の診断は穿通胎盤(せんつうたいばん)なる高度の癒着ならともかく、中度・軽度の癒着の場合は極めて難しいこと、さらに被告医師が女児を娩出させた後に、胎盤を剥離させるという処置をとるまで、癒着胎盤であるとの認識がなかったとの弁護側反論が、それである。
以上を前提に弁護側は、帝王切開の術中に癒着胎盤と判明した場合は、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出に移行するより、胎盤を剥離させる作業を継続し、その後の出血等の状況を見ながら、剥離の継続か、ひとまず剥離を中止して子宮動脈の遮断術あるいは子宮全摘出に移行するかを判断するのが臨床の実際であると、被告医師の採った行為の妥当性を主張したのである。
右の如く、本件の中心的争点は、帝王切開の術中に、癒着胎盤と判明した場合、直ちに胎盤剥離を中止するのが本件当時の医療水準に合致する行為なのか、それとも、剥離を継続し、その後の出血等の状況を勘案しつつ、場合によっては子宮全摘出に移行するのが医療水準にかなうのか、に存したと言ってよい。
そして、裁判所は、両者の主張を精査した上で、検察官の「癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術等に移行する事が本件当時の医学的準則であり、本件において被告人には胎盤剥離を中止する義務があった」との主張を退けたのである。
裁判所は、その理由として、「検察官は、一部の医学舎やC鑑定に依拠した医学的準則を主張しているのであるが、これが医師らに広く認識され、その医学的準則に則した臨床例が多く存在するといった点に関する立証はされていないのであって、その医学的準則が、上記の程度に一般性や通有性を具備したものであるとの証明はされていない。」ことを挙げた。判決は、処々に表れるその文言から、一般の「産科医」を基準に客観的注意義務の存否を判断する「新過失論」に依拠しているものと思われ、その判断と結論は妥当なものであった。しかし、ここに言う、“医学的準則の一般性、通有性”が、ひとたび本件を離れた場合、一体何を意味するのか、判決文ではそれが十全に明らかにされているとは言えないように思われた。
本稿は、そのような問題意識から、大野病院判決で争点となった、“医療水準”という概念道具の内容を精査し、医療の裁量性と医療水準の関係性について若干の考察を加えるものである。
二 医療水準の起源
“医療水準”とひとロに言っても、当該概念は民事、刑事の両過失にまたがり存在するので、その由来と実質をまず、明らかにせねばならない。そこで翻って考えるに、“医療水準”という概念道具は、その起源を辿れば、もともと民事過失の有無を判断する上で、その分水嶺としての機能を果たしてきたと言ってよい。例えば、著名な未熟児網膜症裁判では、事件当時、医師に新種の治療法「光凝固法」の説明義務が課せられていたかの判断に際し、医師の過失の判断基準となりうる医療水準の段階を、当初、最上位の狭義の医療水準(一般に承認されている段階)に求めることで、患者側の訴えを排斥する方向に機能していたのである。
すなわち、実験段階の治療方法や研究者のみに知られているような先進的な治療方法を、臨床の場の医師が履行すべき注意義務の範躊から排斥し、現実妹を欠く過大な注意義務を医師に負わせることを防ぎ、一定の線引きをしていたのである。
しかしながら、その反射的効果として、当該概念は、現に行われている治療方法を肯定する機能が大きく、医師をして医学の急速な進歩・発展に対応させる義務、あるいは研鑽義務を推進する契機を有していないという側面があったことも否めない。殊に、ある診断・治療の方法が広範囲に定着普遍化して初めて医療水準を形成すると解すると、患者にとり新種の方法による診断・治療を受ける機会が制限されるということになりかねず、医師も当該医療慣行に安住し、硬直した判断を常態化させる危険性すらあったのである。その意味からすれば、その後判例により、“医療水準”の意妹付けが徐々に修正され、それが段階的、動態的に把握されることで、患者救済の方向を歩んでいったことは、妥当な流れと言ってよかろう。
一方、本稿で精査する刑事過失における“医療水準”という概念は、民事過失における機能のそれとは異なり、医療の裁量性との関係で精緻な組み立てを必要とするものであると言ってよい。
三 刑事過失における医療水準の特殊性
その本質を明らかにするためには、医療刑事過失と医療水準の関係を少なくとも四つに類型化し、分析を試みる必要があると思われる。
すなわち、
①明確に医療水準に反する過失を筆頭に
②医療の裁量性が問題となる過失
③事後的に医療水準未満と判明したケースと過失判断
④極限的治験水準における過失判断
がそれである。さしずめ、大野病院事件との関連性で言えば、上記②の類型での過失判断が重要となりうる。
第一類型の明確に医療水準に反する過失とは、過失自体が医療水準を場として議論が可能な過失であり、過去に刑事裁判で争われた事例を検討すると、この類型には、まず、第一に薬や器具の使用法に関する不適合事例、第二に手術中あるいは手術後の管理面が医療水準に反する事例、さらに問診行為が医療水準に合致しなかったケースなどが挙げられうる。
この類型は、医療水準という場から、医師の行為が明白に逸脱している点で、比較的、過失の認定がなされやすい。
たとえば、近時の著名な事例、前立腺癌の摘出手術で男性患者(当時六〇歳)が、手術後に死亡した事故(東京慈恵会医科大学青戸病院事件)を例にとれば、腹腔鏡下前立腺摘出手術という、難度の高い術式を医師が採る場合、まず、医師が高度な専門性を有する医師集団に所属し、技術的にも、難度の高い術式を採りうる能力を具備していることが必要となる。
そして、もし、医師らが「本術式」を安全に施行するための知識・技術および経験を持ち合わせていなければ、「本術式」の施行自体、当初より回避されるべきであろうし、少なくとも、早期に「本術式」の施行を中止し、通常の「開腹手術」に移行することが結果回避義務行為としての「基準行為」に合致すると位置づけられ、それに反すれば過失ありとされるわけである。
四 医療の裁量性が問題となる刑事過失
これに比して、第二の類型である医療の裁量性が問題となる過失については、虫垂炎手術時の大腸切除事件のごとく、事がやや複雑となる。
事例は、「盲腸のX」と呼ばれる被告医師が、虫垂切除手術に際し、腹部を二cmほどしか切開しない独自に考案された手術法を採っていたところ、ある日、被告医師の内科外科医院において、急性虫垂炎の患者A(当時12歳)の虫垂切除に際し、虫垂と大腸壁の一部を取り違え、あやまってそれを長さ約五回幅約二・五cmにわたり切除し、他院に転送後、そこで緊急手術がなされたものの、患者を重度の汎発性腹膜炎で死亡させたという事案である。
医師に禁錮一年、執行猶予四年の判決が下された本件が極めて興味深いのは、被告医師が医学書で禁じられている二cmの腹部切開により虫垂の切除手術を施行し、過去に一万例の成功例がある点である。もちろん、医学書の命じる虫垂炎の正しい手術法が、四~五cmの切開を正しい医術的正当性とし、それに反し、創口を小さくすることは、“手術野”が狭くなり、手術部位の確認を困難たらしめるから、厳に慎むべき行為であると位置づけているならば、それは狭義の医療水準として要求される一般に承認された医術的正当性を、医師Xは行為時に採っていないことになる。
しかしながら、医療の裁量性を広く解釈すると、被告医師の行為を擁護することも何らできないわけではない。
状況から察するに、被告医師Xが虫垂炎手術に際し、腹部切開を他の医師が通常行う処置の約半分である2cmにとどめる方法を採っていたのは、手術創が小さければ患者の肉体的負担も少なくなり、回復を速めるメリットが存在するからである。過去に一万例の施行実績があることを考えても、手術後の傷痕の程度から、多くの患者が当該手術を望み、医師Xも、患者のQOL(生活・生命の質)を考慮するあまり、医療の裁量性として許容されうる方法を採っていたとも考えられるからである。では、医師Xの行為は、医療の裁量性との関係で、どのように把握されるべきか。
裁判所は、この点について深く言及していないが、医療水準・医療の裁量性との関連で言えば、以下のような点が重要となろう。
まず、着眼すべきは、Xの行為が、医学が要求する適正なプロセスを踏んでいない点である。すなわち、医学書の命じる狭義の医療水準にある行為を、医師Xが修正する、ないし否定するのならば、自らの手術事例、これまでの様々な虫垂炎手術事例において、患者の年齢、男女の別、虫垂炎の進行度、患者の腹部の肥厚度などの別で、Xは独自の手術経過に差異があったか、また、手術時間はどうかなどの詳細を外科学会に報告し、自らの手術法に関する症例研究を示し、公にその是非を問うべきであったのである。
医療の形成プロセスは、治験水準にある新療法に対する関心度が、医療現場で高まり、追試例が増え、母集団として評価に堪えられる症例数の累積と検討を経て、一応の評価が得られる段階になれば、当初、治験水準にあった新療法も医学水準レベルヘと脱皮し、移行していくことになるのであり、一万例に及ぶ施行実績から考えるならば、それを自己に特有な“自己医療慣行”として秘すのではなく、医学書に記載のある標準的治療から逸脱する“術式”の評価を、しかるベき‘「医療集団」にはかり、その是非を問うべきであったのである。
五 下級審に共通する判断枠組み
言外の意味を汲み取れば、ここには、福島地裁が判決文中で示した、“医学的準則に則した臨床例が多く存在すること”、その医学的準則が、“一般性や通有性を具備したものであること”と共通の判断枠組みが根底に存在していると言えまいか。
右の如き判断の枠組みは、著名な「プラスノーゲンS」による豊胸術死亡事件の判決にも見られないではない。
本件は、整形外科医である被告人が、女性患者の求めにより、いわゆる豊胸術を行うため、同女の左右胸部に、ワセリンを主体とした、「プラスノーゲンS」と称する薬液を乳房底部の乳腺下結合組織に前後二回に分けて注入したところ、第二回目の注入を受けた直後に患者が気分の不快を訴え、約七時間後に死亡したという事案であるが、医師の採った薬液の注入方法、薬液の注入量の調整などに、医師の業務上の注意義務違反があると主張する検察に対し、裁判所は整形外科医の行為の医療水準適合性を探っているからである。
判決は、美容整形術も、社会的に有用なものとしてその存在価値を認められるべき広義の医療行為に属すると位置づけた上で、施術当時の美容整形医一般の技術水準に照らし、あるいは自己または同業の積み重ねた研究成果や多数の経験に照らして、学問的技術能力をもって医師一般の目から観察して危険でないと判断される手段、方法により施術が行われたときは、たとえ、後日にいたりその手段、方法に、施術当時において予測されなかった危険を伴うことが判明したとしても、過失を認めるべきでないと判示し、小規模な領域とは言え、しかるべき臨床例の存在を考慮した。
個別・具体的には、被告医師が、被害者の豊乳術を施行するまでに約五〇〇例の豊乳術を施行し、また、所属する日比谷整形外科医院全体では、一五〇〇例の豊乳術が施行され、同様な手技・手法で同術式を施行し、一度も事故がなかった点に少なからず“一般性・通有性”を認めているのである。
六 大野病院判決の検討
下級審とはいえ、これまでの裁判例の検討から、裁判所が過失判断の基準としている要素を抽出すれば、それはひと言で言えば、医師の行為時における行為の適切性を、医療水準適合性の観点から、一貫して追求しているということである。つまり、医師の行為当時の事実上の行動基準が一応の合理性を持っている限り、行動基準に従った行為について刑法的違法性を肯定することには慎重でなければならないとの考えが、内在しているのである。
その意味から、大野病院判決において裁判所が、一部の医学書およびC鑑定に依拠する検察側主張を退け、被告医師の行為当時、同一領域で産科医療に従事する臨床医の“行為群”換言するならば“医療群”がいかなる「行為のベクトル」を形成していたかに目を向けた点は、意義深い。
冒頭に示した裁判所の判断に付言するならば、裁判所は、過去に一万例の分娩を経験した東北大学医学部産婦人科教授や同様に周産期医療の専門家である宮崎大学医学部産婦人科教授らが遭遇したすべての癒着胎盤の症例に着眼した。そして、胎盤の用子剥離(手による剥離)を開始した場合に、胎盤剥離の完了を優先する旨の彼らの証言から、癒着胎盤の処理について、開腹前診断で穿通胎盤や重い嵌入胎盤と診断されたもの、また、癒着面が強く、用手剥離が不能なものは剥離せずに子宮摘出するのがわが国の医療水準とする弁護側主張に、親和性を示したのである。一方、検察側の証人は、過去に癒着胎盤の手術経験が皆無で、本件の如く稀有な癒着胎盤の判断に際し、適格性を欠いているとしたのである。
事件は、周産期医療における産科医の標準的行為の一群が、一部の医師の判断や医学書と齟齬をきたす事例であり、ある意味、定型的な判断が可能な事例であった。
本件で求められる「医学的準則の一般性・通有性」は、周産期医療の産科医師に広く認識される“癒着胎盤”の処置であり、医師がとるべき行動準則の選択に際し、とりたてて躊躇はなかったと推測しうるからである。
しかし、本件において、例えば胎盤剥離を継続せず、子宮摘出に移行することを適切だとする産科医が、剥離の継続を適切とする医師よりも多数である場合はどうであろうか。
また、被告医師の行為を否定する医学書と肯定する医学書の数が拮抗している場合はどうか。それが論文であればその当否はどうか。限界事例として、解き明かさねばならない問題がないではない。さらに言及すれば、薬害エイズ事件で露呈した以下のような問題もある。
すなわち、医学界に広く知られ、日常的に施行されている治療法(血友病治療における非加熱製剤の使用)が、知識の体系として確固不動のものではなく、新たな病理現象(AIDS)との関係で従来とは異なる仮説が水面下で形成されつつあるようなケースである。この場合、行為時に当該治療法の医療水準性を確信して、それに取り組んだ医師は刑法上どう評価されるべきか。
七 医療刑事過失の判断枠組み(私見)
1 一般に承認された「狭義の医療水準」における過失判断
以上の難題もふまえ、医療水準と医療の裁量性の両者を考慮しつつ、医療過誤に関し、一応の刑法的判断の枠組みを示すならば、およそ以下のように位置づけられまいか。
まず、過失認定の基準として、行為者(医師)の主観ないし、心理的状態を重視する過失の構成に傾斜することは、過失犯処罰、殊に医療刑事過失の判断に、果たしてなじむか、という点が指摘されねばならない。
何故ならば治療行為の過失判断に際し、中核に据えられるべき要素が、医学を支える科学法則である以上、それが命じる準則に力点を置いた行為の遂行が医師には求められているからである。彼は、法的判断に先行する基準として、定立された医療水準に照らし、日々行動しているはずである。そして、もしそうであるならば、彼の行為時における一般的な医学・医療の水準を確定し、医師がその水準から離反したか、換言するならば基準行為からの逸脱の程度がどうかで刑事過失の成否は決せられるべきである。
その際、医師に課せられるべき注意義務は、事前の(ex ante)観点から、対象となる医療群に属し、義務を忠実に履行する平均的医師に期待される注意がその基準とされるべきである。
右の如き過失の構成であれば、ヴェルツェルが過失の注意義務の内容として唱えた、「社会生活上必要な注意」といわれる概念を、医療の範躊で「医療行為遂行上必要な注意」という形態で客観化することを可能とし、現時点での医学・医療を支配し、医療従事者に正当化根拠を提示する「医療水準」に、まさに、その客観化の役割を担わせることができる。
そして、対象となる治療行為が「狭義の医療水準」に位置する場合、右の解釈原理に従えば、事は明瞭である。大野病院の医師の如く、彼が定立された医療水準と同方向を向いており、そこからの離脱が認められなければ、彼の行為は適法である。そして、当該原理を敷衍させれば、医師の施行する治療行為が常態化しており、行為時に一般に承認されている場合、たとえ医師の行為当時、認識不可能な事象があり、その影響で患者に悪結果が生じたとしても、その実体が当時の医学・科学の法則から不明であれば、医師は、その時点の自然科学の法則を遵守している限り、刑事過失に問擬されぬというテーゼが導けるはずである。
同様に、「狭義の医療水準」に医師が同化している以上、彼の行為が厳密な科学法則によれば、「医療水準」未満にあると、事後的に判明しようとも、行為当時に自身が類型化される集団の平均的医師がそれを採用していた場合、彼の刑事過失は否定されねばならない。
2 先端医療である「医学水準」以下における過失判断
治療行為の医療水準、医学的準則が最上位に位置するケースでは過失認定に際し、明確な判断が導けるケースは比較的多かろう。しかし、治療行為の成熟度が最上位の水準ほどの普遍性を具備しない、所謂“医学水準”レベルにおいてはどうであろうか。
発生事例が稀少なためか、大野病院判決を含め、過去の刑事裁判例において、明確に“医学水準”レベルの治療行為に対する過失判断に論究するものは見当たらないが、私はこの段階の治療行為においても、小規模の医療群が形成されている以上、先進的医療機関である大学病院や地域の基幹病院において、当該医学水準レベルの治療法が施行されたとしても、“医学的準則の一般性・通有性“は安易に否定されるべきではないと考える。
確かに「医学水準」段階は、治験段階がようやく母集団として評価に堪えうる症例数の累積と検討を経て、一応の評価が与えられる時期にさしかかっているものの、未だ未知の領域を完全に脱していないと想定されよう。しかしながら、臨床医学は日々進歩しており、その知識の体系は確固不動ではなく、特にその先端領域においては常に新たな病理現象に関する仮説が生成発展しつつあり、そのうちのあるものは経験科学的な検証に堪えることで、確実な知識として臨床医学の知識体系の中に定着していくのである。このような現況にあって、「狭義の医療水準」を最上位とあがめ、臨床医学の最新の仮説が具体的可能性のあるものとして認められるべき水準に達してこそ、正当化の水準とすることは、動的な現代医療の側面を看過しているといえるからである。
このように考えると、医療水準は、ひとえに一般に承認されたレベルのみならず、個別的具体的状況下で医療の裁量性との関係で多様化が許容されるはずである。
すなわち、年齢、体力など患者の身体条件、患者の病状と進行の程度、病院の規模・先進性と行為環境、医師の手技上の能力、患者の自己決定の内容など、一定の診療における具体的状況下において、狭い範躊であれ“一般性・通有性”を具備する治療行為がありうる。先述した限界事例に道筋を示す形で答えれば、個別・具体的状況下で医師の採った行為の医療水準性が、少なくとも医学水準レベルにあり、患者の同意も得られ、医師の行為の適切性が示されれば、自身の選択した手技とは,相容れぬ手技・手法、それを否定する文献、それに疑念を呈示する論文の存在があろうとも、直ちに彼の行為は否定されるべきではない。すなわち、医学水準に合致した注意基準を医師が堅持している以上、医師が過失に問擬されるべきではない。もちろん、行為時に、複数の治療行為が存在する場合、医師は、慎重に治療行為の成熱度を比較極量し、より危険の少ない行為を採ることが望ましかろう。しかし、その成熟度の差異が、医療の裁量性の範躊にあれば、患者への侵襲度、患者の同意の強度を考慮し、医師は、未熟な水準の治療行為をも選択しうる。
また、たとえ医学水準未満の治療行為であろうとも、患者の病状から彼の生命に危険が追っており、他に代替可能な治療法が存在しない場合、医師は、十分なインフォームド・コンセントを経て、最小限の水準に位置する治療法を施行しうる。ただし、医師の「基準行為」を画する医療水準が、最下限に位置する本件においては、権利主作者である患者の自己決定・同意が、治療の旅行を牽引している場合、本来、増強されるべき医師の注意義務の程度が、実質的に減殺される可能性もあるのではなかろうか。
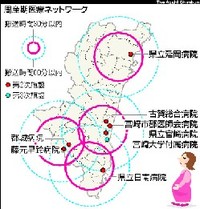

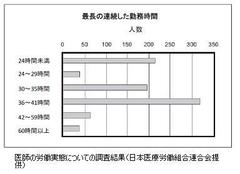


最近のコメント