(関連目次)→生殖医療に関すること 代理母問題など 目次
ぽち→ 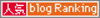
(投稿:by 僻地の産科医)
日本医師会雑誌がちょうど生殖医療、わかりやすくいうと
不妊治療について特集していたのでo(^-^)o!!!
いくつかあげていきます。
生殖補助技術への対応―世界と日本―
米本昌平
(日医雑誌第137巻・第1号/平成20(2008)年4月 p63-66)
I.生殖補助技術と宗教
1978年に世界最初の体外受精児が誕生すると,欧米社会を中心に生殖補助技術に関して強い社会的関心が沸き起こり,さまざまな形でこれを規制の対象に繰り込んできた.この「生殖補助技術の焦点化」という事態は,一面でキリスト教教義と深い関係がある.近代キリスト教は,人間の発生に関して精緻な教義を築いてきた.他方で欧米社会では,それまで犯罪とされた人工妊娠中絶が1970年代を通して合法化されたため,ヒトの発生のどの時点をもって人間と見なすかが,重大関心事となっていた.そこに体外受精技術が出現したため,生殖補助技術の規制は一気に現実味を帯びることになったのである.
ただしその規制の在り方は,それぞれの国の統治形態や医療の供給形態を反映するものとなるため,生殖補助技術の対応の在り方を国際的に比較してみると,法規制が進んでいる欧州,連邦レベルの法規制がないアメリカ,立法化の動きが鈍く学会規制の下にある日本という,3つの型に集約することができる.
キリスト教の教えに従えば,男女の間に愛が生まれ,祝福を受けて結婚し,セックスを介して子が授けられるこの一連の事柄は,神の深い恩寵による.そのため,セックスを迂回するかにみえる体外受精技術の出現は,当時の欧米社会には強い衝撃をもって迎えられた.この事態を受けて西欧諸国では,1980年代を通して生殖補助技術に関する技術評価報告がいくつかまとめられ,これを踏まえて1990年代前半には生殖技術法が成立した.影響力は衰えたとはいえ,宗教は今日でもなお価値観の供給源として社会的意義が大きく,これらの法律のなかには,キリスト教教義の世俗的表現に近いものを法律条文として採用している例がある.もともと生殖補助技術(assisted reproductive technology ;ART)という言葉には,神の恩寵である手作りに関し,ほんのわずか人間の側か手を貸す,という意味合いが込められている.
ところで『コーラン』では,胎児は3か月までは水みたいなものとされており,イスラム諸国の間に生殖補助技術が浸透していった場合,その社会的対応の在り方がどうなるかは予想しがたい.ただし,結婚については厳しい規定があり,女性の側が一方的に遺伝病チェックを求められるおそれなどを指摘する声もある.
西欧諸国の多くはまた福祉国家を確立させており,医療は社会的給付という性格を帯び,供給面からも規制されることになる.この点で,医療の大半が自由市場に委ねられているアメリカとは規制の形態が異なってくる.このような点を考慮し,公開文献とインターネット情報によってイギリス,フランス、オーストリア,アメリカの対応を見てみよう.
Ⅱ.イギリス:独立官庁による一元的管理
イギリスでは,世界初の体外受精児が生まれると,人間の胚を体外で作製することを問題視する声が大きくなり,政府は1982年に生殖補助技術一般に関して調査し対応策を考える委員会を置いた.委員長の哲学者メアリー・ウォーノックの名をとって「ウォーノック委員会」と呼ばれるこの委員会は,1984年に64項目の勧告を含む報告書を保健省に提出した.これを起点に、1990年には「ヒト受精および胚研究法」(HFE法)が制定され,この法律によって,生殖補助技術だけではなくヒト胚研究をも一元的に管理する行政庁「ヒト受精および胚研究認可庁」(HFEA)が設置された.
HFE法は,クローン人間やキメラ人間の作製を禁止する一方で,それ以外の生殖補助技術については,HFEAによる施設認可とし,体外受精,AID(非配偶者問人工授精),提供精子・卵子による体外受精,着床前診断,胚提供に関してはHFEAが作成する実施要綱や見解に従うこととし,実施内容はHFEAに報告が義務付けられる.このためイギリスは,生殖補助技術に関する体系的なデータが明らかになっている数少ない国となっている.またHFE法は,親子関係についても規定しており,懐胎した女性が母親であり,また懐胎した女性の夫は施術に同意していないことが立証されない限り父親となる,と規定している.
2006年現在で,体外受精の認可施設は69施設,AIDの場合は82施設である.7組に1組のカップルが何らかの理由により不妊とみられ,出生児の約1%がIVF(in vitro fertilization)治療およびAID治療によって生まれた子どもと推計されている.
なお先行して,営利目的での代理母契約を禁止する「代理出産取り決め法」が1985年に制定されている.一般にイギリスは,他の西欧諸国とは異なって,生殖補助技術に許容的であり,プラグマティックな対応策をとっている.
Ⅲ.フランス:生命倫理に関する体系的法改正と行政による規制
1982年にフランス初の体外受精児の出産が報告されると,大統領直属の国家倫理諮問委員会などから報告書が出され,これに続く長い議論を経て1994年には生命倫理関連4法が公布された.このなかの「人体の尊重に関する法律」および「人体の要素と産物の提供と利用,生殖補助技術と出生前診断に関する法律」において,生殖補助技術一般に関する規定が設けられた.さらに2004年の法改正によって,先端補助技術の管理を担う生物医療庁(Agence de Biomdecine)が設置され,生殖細胞の輸出入や国境を越える胚の移転の許可,生殖補助技術の研究者に関する認可・報告制度などが付された.法律により代理母の契約は無効とされている.
フランスにおいては,法律の細則を定める行政令が,治療を受けられるカップルの条件,第三者の配偶子や胚を必要とする生殖補助技術,治療を受ける場合の事前面談,生殖組織の保存など生殖補助技術の範囲について細かく規定している.これによると,自然なプロセス以外で生殖を可能にする技術すべてが生殖補助技術と定義され,その実施者は生物医療庁の認可を,また実施施設は,保健大臣が策定する保健医療組織計画に基づき,地域保健当局の許可を受ける必要がある.生物医療庁の2005年の年次報告によると,2004年時点で認可を受けている医療機関は108施設,生殖医学研究機関は210施設である.2004年の出生数約76万7,000人のうち2.3%が生殖補助技術による出生とされている.
IV.オーストリア:キリスト教的価値を反映させた法規制
オーストリアは,国民の大半がカトリック教徒(日本外務省のデータでは78%)であり,世界初の体外受精児が生まれると,大々的な社会的議論が巻き起こった.オーストリア議会は,1986年に体外受精委員会を置いたが,議会での審議は大幅に遅れ,1992年になって生殖技術法(Fortpflanzungsmedizingesetz)が成立し,合わせて関連する民法典,婚姻法の改正が行われた.生殖技術法で,「医学的補助生殖とは,性交以外の方法で妊娠を引き起こすことに医学的手段を適用することを意味する」とされ,セックスを介さない子作り全般がその対象である.
法律により,治療を受けられるのは結婚もしくは事実婚のカップルであり,体外受精で作成できる受精卵は3個までで,本人の子宮に移植することを前提としている.この法律では,卵や受精卵の譲渡は考えられておらず,また法解釈上,着床前診断は認められないと考えられている.AIDにより生まれた子は,満14歳になると厳格な条件付きであるが出自を知る権利が与えられる.
法律には,「医療関係者は生殖補助技術を行っても,また逆にその実施を拒否しても,共に不利な扱いを受けない」という条文がある.このような明文化が必要になるほど,この国では生殖補助技術についての意見は割れたのである.そのため体外受精は医療保険の対象にはならなかったが,カップルの負担が大き過ぎるとの批判が出され,2000年1月より体外受精基金(IVF-Fonds)による助成が開始された.条件は,治療開始時点で女性40歳以下,男性50歳以下の不妊のカップルに対し,最大4回まで,体外受精の経費の70%を助成するというものである.実施データは,「体外受精登録(IVF-Resiter)」に集約され,実態把握と技術水準の確保のために利用されている.この基金と契約している医療施設は25施設である.
V.アメリカ:個人の選択を大幅に認め,学会見解は参考
元来,「自由の国アメリカ」とは信教の自由を意味し,欧州で抑圧されていた小宗派による宗教移民によって聞かれた国である.このため,宗数的価値に強くかかわる家族観・性・中絶などについては社会的合意に達するのとは逆に意見は大きく割れる傾向にあり,これらの課題は大統領選挙でも繰り返し争点となってきた.特に1973年の連邦最高裁による中絶自由化判決が出て以降,国論は二分し,胎児はどこから人間と認められるべきかという問題に関連する生殖補助技術に関しては,連邦レベルで意思形成の場がもてないでいる.これが,連邦レベルではクローン禁止法すら成立しえない統治構造上の理由である.実際,連邦法としては,「不妊クリニックの誇大広告を規制する法律」(1992年)を除いて,規制法規は存在しない.
宗数的価値にかかわる領域の立法権限は各州に委ねられているため,生殖補助技術の実施条件や,生まれた子どもの法的親子関係などは,関連する各州法や裁判所判決によって決められることになる.各州法があまりばらばらにならないよう,全米レベルの連絡組織があり,ここが1988年に「生殖補助技術で生まれた子どもの地位に関する統一法」,2000年に「統一親子関係法」(2002年改正)などのモデル法を提案しており,これを取り入れている州もある.
また,アメリカの医療の多くは,個人が購入する民間医療保険に委ねられており,とりわけ生殖補助技術は,個人が自己責任によって選択して購入する対象メニューという性格が強い.アメリカ産科学会が1980年代以来,慎重なガイドラインを出しているが,これらは参考情報に近い位置にある.
VI.日本への示唆:生殖技術法の立法化を
以上のように西欧諸国とアメリカでは,生殖補助技術についての規制の在り方は,大きく異なっている.これまで日本では,新しい形の倫理的課題が生じると諸外国に先例を求め,それを準用するのが常であった.そのなかで,着床前診断や代理母など,生殖補助技術の新規な利用の仕方を日本でも認めさせようとする立場の人たちは,「生殖の自己決定」や「幸福追求権」という概念を掲げ,選択の自由を認めるよう訴えてきた.だが,こうして世界を総覧してみると,このような主張はアメリカ的な自由主義理念に立つもので,主要国の間では主流ではないことが分かる.
日本社会は,価値観が多様化してはいないという意味で,欧州型に近い.だが,欧州のように宗教が社会的価値に関する共通で明示的な供給源にはなっていないため,新しく生殖技術法を制定するとしても,規制の大枠を定めるものとなる可能性がある.現在,生殖補助技術の規制は,日本産科婦人科学会の見解に委ねられているが,元来,学会は学術親睦団体であり,医療における施術の管理を行う組織ではなく,そのための法的権限もない.このことも,生殖技術法を必要とする大きな理由である.
そのためにはまず,生殖補助技術に関する包括的な技術評価報告書を作成し,取り組むべき課題の全体像を社会が共有すべきである.また,国境を越えた人の移動がますます自由になっており,この意味でも韓国,台湾,中国など近隣諸国における医療サービスの現状と規制の実態を把握する必要がある.近隣諸国との政策対話を開始することは,日本社会の根底を流れる生命観や家族観を浮かび上がらせる意味でも重要であり,それにより,来るべき生殖技術法の基本を考えるうえでの重要な鍵が得られるはずである.
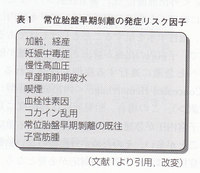
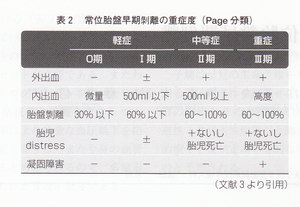

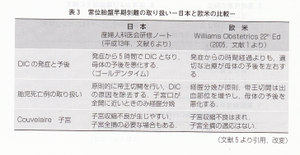
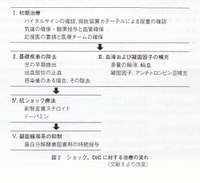
最近のコメント