(関連目次)→子育てを考える 目次 医療政策 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
12月12日に下記のようなニュースがありましたo(^-^)o ..。*♡
出産一時金42万円へ引き上げ 厚労省が正式提示
日本経済新聞 2008年12月13日
http://s02.megalodon.jp/2008-1213-2138-03/www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081213AT3S1202H12122008.html
出産育児一時金、さらに4万円引き上げへ―厚労省
キャリアブレイン 2008年12月12日
http://s02.megalodon.jp/2008-1213-0043-55/www.cabrain.net/news/article/newsId/19650.html
でも、果たして出産一時金、増額されて出生率なんて上がるの?
というのが一市民(&親)としてのソボクな疑問点です。
だって、出産一時金。
もらった時、「らっきー」くらいにしか思いませんでした。
でもって、ランニングコストというものが必要なんです(>_<)!!!
子育てはいろいろ、物入りなのようっ!!
そんでもって、時間もとられます。
共働き世帯であったなら、母親の労働時間短縮による収入減は、
はっきり言って罰ゲームみたいなものです。
共働きの場合、夫がその分頑張ればがんばるほど、
「何で帰ってこないんだぁぁぁっ(>_<)!!!!」
「自分ばっかり働いて楽しやがってっ!!!!」
という思考に走ってしまうくらい、トラブルの元になります。
お隣の韓国では、
「女性の賃金が上がれば出産率が落ち、
男性賃金が上がれば出産率が高くなるという研究結果」
もでているそうです。
ここにこんな良い論文がありましたのでご紹介します ..。*♡
女性労働者の出生行動と金銭的インセンティブ
―健康保険組合データに基づくパネルデータより―
富士通総研(FRI)経済研究所
研究員 河野 敏鑑
http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/report/research/2008/no313.pdf
要旨
本稿は、家計に対する出産に関する一時金が、出生に対し、どのような効果を持つのかを実証的に明らかにしようとするものである。日本の総人口の約4 分の1 は、健康保険組合の被保険者または被扶養者であるが、健康保険組合の半数以上が被保険者または被扶養者に対し、法定の出産育児一時金に上乗せして、独自に付加給付を行っている。 本稿では、健康保険組合のパネルデータを用いて、組合ごとの個別効果を調整した上で、一時金が女性被保険者(女性労働者)の出生率に与える影響を分析した。
その結果、
1.一時金が出生率を上昇させる効果は給与の低い組合でも高い組合でも見られない。
2.報酬が出生率に与える効果は、給与の低い組合では見られるが、給与の高い組合では見られない
ことが分かった。
1. はじめに
1.1 背景と目的
出生率の低下に伴う急速な高齢化の進展は、現在の日本にとって大きな問題である。昭和22(1947)年に4.54、昭和30(1955)年に2.37 であった合計特殊出生率は、平成17(2005)年には、1.26 にまで減少した。それを受けて、総人口に占める65 歳以上の人口の割合、すなわち高齢化率は、昭和25(1950)年には、4.9%にすぎなかったが、平成17(2005)年には、20.1%にまで上昇し、今後も上昇基調が続くことが予想されている。
人口構成の急激な高齢化に伴って、社会保障制度の持続可能性や労働力の不足といった問題が懸念されている。そこで、出生率を回復させるための様々な政策が考えられている。子育ての費用を減らすことで出生率を上げようとする政策も取られており、事実、2006 年の10 月には、公的医療保険における出産育児一時金が1 件あたり30 万円から35 万円へと増額された。
もし、出産に関する一時金が、出産に伴う直接、間接の費用をカバーするに十分大きい額ならば、出生率を上昇させると考えるのも合理的であろう。しかし、リクルート(2003)によれば、出産に伴う費用は、直接的な費用だけでも、66 万6 千円であり、出産育児一時金の35 万円を大きく超えている。金額が少額であるため、出産に関する補助金が出生率に与える影響はそれほど明らかではないと思われるが、両者の関係を実証的に明らかにすることは、重要と考えられる。
本稿は、家計に対する出産に関する一時金が、出生に対し、どのような効果を持つのかを実証的に明らかにしようとするものである。
1.2 調査研究の方法
本稿では、被用者保険の代表例であり、国民皆保険の対象の約4 分の1 が所属している健康保険組合の組合別データを用いて、分析を行った。国民皆保険のもと、健康保険組合は、法律で定められた給付を行うことが義務付けられているが、被保険者や被扶養者に対して、法定給付とは別に付加給付を行うことができる。付加給付は、加入者の自己負担などを軽減するために行われているもので、法定給付に一定の割合あるいは金額を付加金として上乗せして支払われる。出産に関して一時金に付加金を上乗せして支払っている健康保険組合は全体の約半数にのぼる。付加給付額は組合によって異なっているため、この違いを用いれば、一時金の多寡が出生率に与える影響を分析することが可能である。また、本データでは、被保険者と被扶養者を区分して集計されているため、出産に対する一時金の影響を別々に分析することも可能であり、本稿では、女性被保険者(女性労働者)に着目して分析を行った。
1.3 先行研究
出生率と補助金の関係を扱った先行研究をいくつか紹介する。Butz and Ward (1979) とWhittington, Alm, Peters (1990) は、米国の時系列データを用いた研究である。Hyatt and Milne (1991)とZhang, Quan, and Meerbergen (1994)は、カナダの時系列データを用いた研究である。Boyer (1989) は、19 世紀のイギリスの教区ごとのクロスセクションデータを用いた研究である。いずれの研究も、補助金には、出生率を上昇させる効果があることが確認されているが、その効果は小さく、統計的に有意でないとする研究もある。
日本においては、織田(1994)や塚原(1995)などで、児童手当の効果が研究されている。その結果、児童手当の効果は、日本の少子化を止めるためには小さすぎることが分かった。
ただし、これらの研究は、ヴィネット調査と呼ばれる、仮想的な質問とその回答を分析したものなので、実際の行動との間には、多少のギャップがあることを否定できない。原田・高田(1993)は、県ごとのクロスセクションデータを用いて同様の結論を導き出している。
1.4 結論
線形確率モデルを用いて、組合の個別効果と年度ごとの個別効果を考慮したモデルで分析したところ、(1)一時金が女性被保険者の出生率を有意に上昇させる効果は見られないこと、(2) 報酬が出生率に与える効果は、給与の低い組合では見られるが、給与の高い組合では見られないことが分かった。
1.5 本調査研究の特性と本稿の構成
我々の研究が先行研究と異なっている点は少なくとも2つある。一点目は、パネルデータを用いていることである。このため、クロスセクション分析や時系列分析とは異なり、時間を通じても変化しない組合の個別効果をコントロールして分析を行うことが可能である。二点目は、データが女性被保険者(労働者)と被扶養者(専業主婦など)とを区分して集計されているため、両者に対する効果を別々に推計することが可能であることである。
本稿の構成は以下の通りである。第二節で、計量モデルを解説し、第三節では、データについて記述する。第四節で、分析結果を紹介し、第五節が結論である。
2. 計量モデル
出産に関する補助と出生率との関係について、理論的な分析を行った研究として、Becker(1989)がある。もし、家計が子供を持つのか否かを子供を持つことによる費用や便益を考慮に入れて決定しているのであれば、出産に対する補助は出生率を上昇させる。しかしながら、こうした補助金が与える影響は女性労働者と専業主婦とで異なることが予測される。
というのも、女性労働者が出産する場合は、出産や育児に伴って、労働所得が減少するという機会費用が発生するためである。もし、出産に関する補助が、こうした機会費用を埋め合わせるのに十分でなければ、女性労働者は子供を持とうとは思わないかもしれない。
3. データ
本節では、公的医療保険制度にふれつつ、研究に用いたデータを紹介する。日本では、国民皆保険であるので、いずれかの公的医療保険に入らなくてはいけないが、被用者(共済組合や船員保険に加入している者や、常時雇用されていないもので年収130 万円以下の者(60 歳以上の者および障害者は年収が180 万円以下の者)を除く)は、健康保険に加入しなければならない。
健康保険は、健康保険組合と政府(社会保険庁)によって運営されているが、健康保険組合は、一定規模以上の会社や会社の連合体でなければ設立できない。勤務先が健康保険組合を設立している労働者は、被保険者として勤務先の健康保険組合に加入しなくてはならないが、そうでない労働者は、被保険者として政府が管掌する健康保険に加入する。なお、労働者に扶養されているものは、被扶養者として扶養している労働者と同じ制度に加入しなくてはならない。
本稿では、健康保険組合の組合ごとのデータを用いて分析を行う。健康保険組合は、日本の全人口の4分の1しかカバーしていないが、以上のような特性から、主要な会社や業界の労働者やその家族の医療・出生行動をカバーする分析が可能である。
本稿で用いたデータは、2種類のデータソースを利用している。付加給付の基準額については、健康保険組合連合会(1998)および健康保険組合連合会(2002)を利用した。それ以外のデータ、例えば、各組合の出産育児一時金の給付件数や女性被保険者数などは、情報公開法に基づき、厚生労働省保険局から開示を受けたものである。
以上のデータソースをもとに、1998 年度と2002 年度のパネルデータを作成した。パネルデータの作成に当たっては、1.明らかに数値が異常値である組合を除外し、2.出産育児付加金の金額が、標準報酬月額や出産に要した実費に依存するなどのために、個別に受領した金額が判明しない組合を除外し、3.両年度を通じてともに存在した組合に限定した。その結果、分析の対象となった組合は1,649 組合となった。
“mbrate” (女性被保険者の出生率)は、各年度ごとの被保険者に対する出産育児一時金の支給件数を女性被保険者数で除したものとした。すなわち、本稿で用いられる出生率は、一般に広く用いられる合計特殊出生率ではなく、粗出生率に近いものであるといえる。標準報酬月額は、保険料の算定の基礎となるもので、第1 級(98,000 円)から、第39 級(980,000 円)まで分けられていた。各被保険者の報酬3 は、いずれかの等級に区分されている。おおむね、被保険者の税・保険料を引く前の月収と考えて差し支えないと考える。“fem_salary”と“male_salary”は、それぞれ、女性と男性の被保険者の平均標準報酬月額である。単位は1,000 円である。
組合管掌健康保険では、保険料率は、法令の制約の範囲内ではあるものの、各組合が自由に定めることができる。また、保険料は、原則として労使折半であるが、組合が規約で定めることにより、使用者の負担を半分以上に引き上げることができる。そこで、使用者が負担する保険料の料率を “cost_firm”とした。単位は、パーミル(1000 分の1)である。1998 年度および2002 年度において、出産育児一時金の法定給付は、1 件30 万円であった。組合によって、出産育児一時金の付加給付額は異なるが、 “msubsidy”を女性被保険者に対する付加給付額とし、“ssubsidy”を被保険者の妻(家族)に対する付加給付額とした。 なお、女性被保険者の出産に際し、一時金の付加給付を行っている組合は、1998 年度で1,049組合(65.2%)、2002 年度で898 組合(62.3%)であった。また、被保険者の配偶者(専業主婦)の出産に際し、一時金の付加給付を行っている組合は、1998 年度で1,054 組合(65.5%)、2002年度で882 組合(61.2%)であった。
なお、女性被保険者の出産に際し、一時金の付加給付を行っている組合は、1998 年度で1,049組合(65.2%)、2002 年度で898 組合(62.3%)であった。また、被保険者の配偶者(専業主婦)の出産に際し、一時金の付加給付を行っている組合は、1998 年度で1,054 組合(65.5%)、2002年度で882 組合(61.2%)であった。
平均年齢であるが、データから被保険者の男女別の平均年齢は分かるが、配偶者を含む被扶養者の平均年齢は残念ながら分からない。 本稿では、“male_age”を男性被保険者の平均年齢とし、“female_age”を女性被保険者の平均年齢とした。また、被保険者に占める女性被保険者の割合は出生率に大きな影響を与えると考え、その割合を “fem_rate”とした。図表 1 に変数の定義を記載し、また、図表 2 に、記述統計量を記載した。
本稿では、“male_age”を男性被保険者の平均年齢とし、“female_age”を女性被保険者の平均年齢とした。また、被保険者に占める女性被保険者の割合は出生率に大きな影響を与えると考え、その割合を “fem_rate”とした。図表 1 に変数の定義を記載し、また、図表 2 に、記述統計量を記載した。
今回の分析では健康保険組合を低所得グループと高所得グループに分けた。この区分けであるが、1998 年度か2002 年度に女性の標準報酬月額が、225,964 円(組合ごとの女性の平均標準報酬月額の中央値)を上回っている組合を高所得グループとし、残りの組合を低所得グループとした。
出生率を見てみると、女性労働者では、高所得グループの方が出生率は高くなっている。また、出産育児一時金の付加給付額は、低所得グループよりと高所得グループの方が高くなっている。
4. 分析結果 推計結果は、図表 3 に記載されている。本稿では、大きく分けて2種類のモデルに基づいて推計を行った。最初のモデルは、出産育児一時金の付加給付額 (msubsidy)、女性被保険者の平均給与(female_salary)、 女性被保険者の平均年齢 (female_age) そして、その二乗項(female_age2) と定数項を説明変数とした。二つ目のモデルでは、以上に加えてfem_rate, male_salary, male_age, male_age2, ssubsidy そして cost_firm を各健康保険組合の属性をコントロールするために説明変数に加えて分析を行った。固定効果モデルと変量効果モデルの双方で分析を行ったが、Breusch-Pagan テスト(Breusch and Pagan 1979) によれば、組合に個別効果が存在することが示唆されている。図表3,4,5 には、Breusch-Pagan テストの結果は記載していないが、Hausman (1978)によるハウスマンテストの結果として、そのp 値を記載した。
推計結果は、図表 3 に記載されている。本稿では、大きく分けて2種類のモデルに基づいて推計を行った。最初のモデルは、出産育児一時金の付加給付額 (msubsidy)、女性被保険者の平均給与(female_salary)、 女性被保険者の平均年齢 (female_age) そして、その二乗項(female_age2) と定数項を説明変数とした。二つ目のモデルでは、以上に加えてfem_rate, male_salary, male_age, male_age2, ssubsidy そして cost_firm を各健康保険組合の属性をコントロールするために説明変数に加えて分析を行った。固定効果モデルと変量効果モデルの双方で分析を行ったが、Breusch-Pagan テスト(Breusch and Pagan 1979) によれば、組合に個別効果が存在することが示唆されている。図表3,4,5 には、Breusch-Pagan テストの結果は記載していないが、Hausman (1978)によるハウスマンテストの結果として、そのp 値を記載した。
図表3 には、全ての組合のデータを用いた分析結果が記載されている。このデータによれば、女性労働者の出生率に一時金は有意な影響を与えていないことが分かる。(説明変数を少なくした変量効果モデルでは、一時金は出生率に有意に負の効果を与えている。しかし、ハウスマンテストによれば、変量効果モデルは5%の有意水準で棄却されることが分かる。)
説明変数を少なくした固定効果モデルでは、女性被保険者の平均給与が出生率に有意に正の効果を持っていることが分かる。しかしながら、その効果は給与を月10 万円引き上げても、出生率を0.5%引き上げる程度であり、小さいことがわかる。
 図表4 は、低所得グループのデータを用いた分析結果である。ここでも、出産の一時金は、女性労働者の出生率に対して統計的に有意な結果を与えていないことが分かる。ただし、給与が出生率に与える影響は、変量効果モデルで見る限り、統計的に有意に正であり、全データを用いた分析に比べて大きいことが分かる。(ハウスマンテストによれば、変量効果モデルが有意に棄却できる水準には達していない。) 女性の平均月収が10 万円上昇すると、女性労働者の出生率が0.9%上昇することが分かる。
図表4 は、低所得グループのデータを用いた分析結果である。ここでも、出産の一時金は、女性労働者の出生率に対して統計的に有意な結果を与えていないことが分かる。ただし、給与が出生率に与える影響は、変量効果モデルで見る限り、統計的に有意に正であり、全データを用いた分析に比べて大きいことが分かる。(ハウスマンテストによれば、変量効果モデルが有意に棄却できる水準には達していない。) 女性の平均月収が10 万円上昇すると、女性労働者の出生率が0.9%上昇することが分かる。
女性被保険者の平均年齢とその二乗項の係数から計算すると、説明変数を少なくした変量効果モデル(一番左の列)では、女性労働者の出生率が最も高くなるのは、27 歳のときであり、説明変数を多くした変量効果モデル(左から3 列目)では、女性労働者の出生率が最も高くなるのは、24 歳のときである。
 図表5 は、高所得グループのデータを用いた分析結果である。4 つのモデルのうち、3 つで女性労働者の出産に関する一時金が統計的に有意な影響を与えていない。しかも、残りの1 つ(説明変数の少ない変量効果モデル)では、有意に負の影響を与えていることが分かった。このモデルに従えば、女性の平均年齢とその二乗項の係数から計算すると、女性労働者の出生率が最も高くなるのは、34 歳のときであり、女性被保険者の給与が出生率に統計的に有意な影響を与えていないことが分かる。
図表5 は、高所得グループのデータを用いた分析結果である。4 つのモデルのうち、3 つで女性労働者の出産に関する一時金が統計的に有意な影響を与えていない。しかも、残りの1 つ(説明変数の少ない変量効果モデル)では、有意に負の影響を与えていることが分かった。このモデルに従えば、女性の平均年齢とその二乗項の係数から計算すると、女性労働者の出生率が最も高くなるのは、34 歳のときであり、女性被保険者の給与が出生率に統計的に有意な影響を与えていないことが分かる。
以上まとめると、出産に関する一時金自体が、女性労働者の出生率に与える影響はきわめて小さいことが分かった。また、低所得の組合にいる女性にとっては、給与の上昇が、小さいとはいえ有意に出生率にプラスの影響を与えることが分かった。
5. 終わりに
本稿では、健康保険組合のパネルデータを用いて、組合固有の効果を考慮に入れた上で、出産の一時金が女性被保険者に与える影響について、分析を行った。その結果、出産の一時金は出生率に有意に正の影響を与えてはおらず、給与が出生率に影響を与えるのは低所得グループに限られることが分かった。
法定の出産育児一時金は、2006 年10 月に1 件30 万円から、35 万円に増額されている。こうした政策変更は少子化対策の一環として行われており、金銭的な給付が出生率を上昇させるとの期待が背景にあるものと考えられる。しかしながら、本稿の結果によれば、一時的な金銭的給付は、出生行動にほとんど影響を与えないと思われる。
給与(標準報酬月額)が、出生率に影響を与えていることについては、2つの解釈が考えられる。一つは、定常的に給与が高ければ、金銭的に安定し、出生行動を促す可能性があること。もう一つは、男女差別が少ない会社(事業主)では、女性の給与が高くなると同時に、出産や育児をしやすい環境になっており、両者の間では見せかけの相関が生じている可能性がある。いずれの仮説が正しいのかを明らかにすることについては、今後に残された課題である。
改めて言うまでもなく、公的機関の行う政策はその費用対効果が検証されるべきものである。少子化対策として取り上げられる政策手段には、本稿で取り上げた金銭的なものだけではなく、例えば、乳幼児医療費助成制度、保育所の増設や残業の抑制によって仕事と家庭の両立を図るなどの政策も考えられる。こうした政策についても、その費用対効果が論じられるべきであり、金銭的な政策と他の政策との間でその費用対効果の比較を行うことが今後に残された課題であると言えよう。





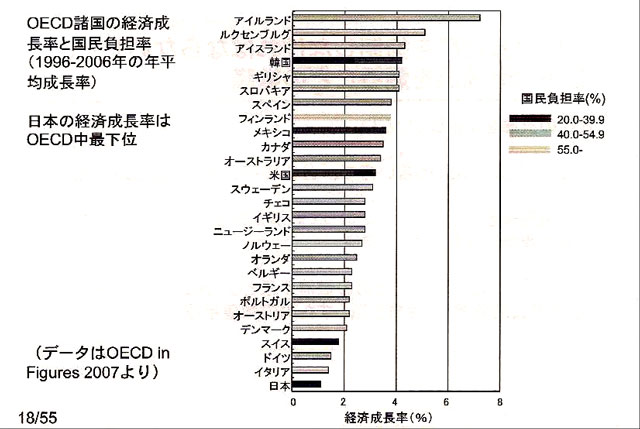
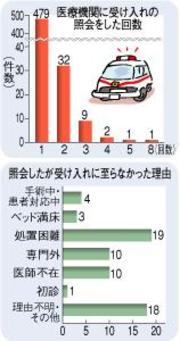
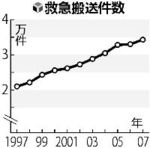
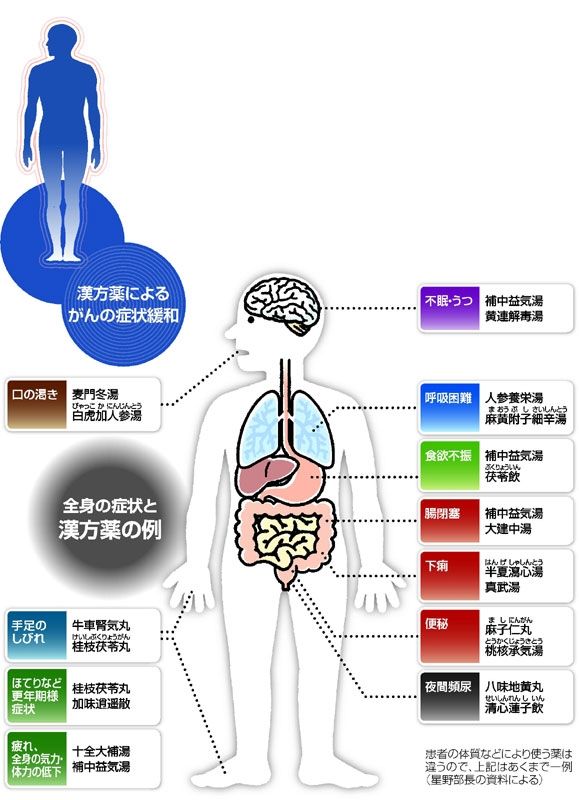
最近のコメント