(関連目次)→小児科の現状 目次 産科医療の現実 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
NICUについて、本当に素晴らしい特集です(>▽<)!!!!
前回分はこちらですo(^-^)o ..。*♡
「一度はデスクに原稿提出していたのですが
納得いかなくなって書き直しをすることにして、
毎日デスクが出勤するギリギリまで書いたという有様でした。」
特に第4回の部分には最後まで迷われたようです。
熊田記者の力作、ぜひぜひご堪能くださいませ(>▽<)!!!
次回が最終回です!
特集「新生児医療、“声なき声”の実態」(3・4)
熊田梨恵
キャリアブレイン 2008年12月10・11日
(1)http://www.cabrain.net/news/article/newsId/19601.html
(2)http://www.cabrain.net/news/article/newsId/19625.html
新生児科医増やす工夫は?
年々増える低出生体重児や長期入院。未熟児の赤ちゃんたちを支える新生児医療の現場は過重労働に疲弊している。どのようにすれば新生児科医を養成し、医療者にとって働きやすい環境に改善していけるのだろうか―。
■学生時代に新生児医療の教育を
青森県立中央病院総合周産期母子医療センターのNICUで働く卒後7年目の宇都宮剛医師。研修後のほとんどの期間、新生児医療に携わってきた。「たまたま当時の上司に声を掛けられて新生児医療にかかわるようになったが、学生の時には赤ちゃんの診察法について学んだぐらいで、NICUについてのきちんとした講義などはなかった」と話す。 新生児科医の養成に関しては、医学部では新生児医療についての講義がほとんどなく、卒後臨床研修でも小児科の中に新生児医療を組み込んでいない研修病院も多いため、学生時代にこの分野を知るきっかけがなく、志す医学部学生が少ないとの指摘がある。埼玉医科大総合医療センター総合周産期母子医療センター長の田村正徳氏は、「卒後研修を実施する国立大学の約6割が新生児臨床研修を実施していない」と話す。新生児医療を教えられる教員の数も少なく、医育機関名簿によると、医育機関の小児科の中で新生児を専門にする教授の割合は、国立大で4.9%、公立大で20.0%、私立大で14.5%にとどまっている。
新生児科医の養成に関しては、医学部では新生児医療についての講義がほとんどなく、卒後臨床研修でも小児科の中に新生児医療を組み込んでいない研修病院も多いため、学生時代にこの分野を知るきっかけがなく、志す医学部学生が少ないとの指摘がある。埼玉医科大総合医療センター総合周産期母子医療センター長の田村正徳氏は、「卒後研修を実施する国立大学の約6割が新生児臨床研修を実施していない」と話す。新生児医療を教えられる教員の数も少なく、医育機関名簿によると、医育機関の小児科の中で新生児を専門にする教授の割合は、国立大で4.9%、公立大で20.0%、私立大で14.5%にとどまっている。
宇都宮氏は、「新生児科は一般小児科と違って、生まれた時から患者さんにかかわれる。未熟児で生まれて人工呼吸をしていて、しゃべれなかった子どもが成長して退院し、外来でどんどん大きくなっていく過程を見る。子どもたちのそういう成長が見られる唯一の科なので、しんどいことも多いが、やりがいもあって楽しい。一度小児科をやりたいと決めた学生は、卒後研修が終わっても小児科を志していることが多い。学生のうちに開業医も見るなどして小児科の魅力を知り、NICUを経験しておくことが必要だと思う」と語る。
青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療管理部門部長の網塚貴介氏は、「ほとんどの都道府県に周産期母子医療センターがあるのだから、大学の臨床実習でセンターでの研修を義務付けるべき」と、医学部生が新生児医療の現場に触れる機会を確保すべきと主張する。
では、現場で既に働いている新生児科医の定着やスキルアップを図るため、国内ではどのような取り組みがあるのだろうか。
■スキルアップ研修で中堅医師を全国から公募-神奈川県
「全国の新生児医療に従事する若手・中堅医師にキャリアアップしてもらい、地方に戻って活躍してもらいたい」と語るのは、神奈川県立こども医療センター新生児科医長の豊島勝昭氏。同センターでは、全国の新生児医療に従事する医師を対象に、同センター小児科で短期の研修を受ける医師を公募する「短期有給研修医制度」を来年度から2年間実施する予定だ。例えば、新生児の心臓手術の経験が少ない地方の病院に勤務する医師が同センターでその技術を学んだり、新生児医療の専門技術を経験の多い専門医から教えてもらったりすることで、能力向上を目指す。これは、豊島氏が県の「職員提案事業制度」に応募して採用されたもので、研修医の報酬などは県が負担する。
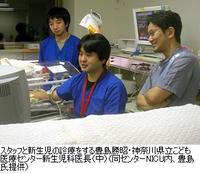 同センターには、早産や出生前診断された重症の先天性の病気、外科手術が必要な病気の新生児が集まる。どんな重度の疾病や障害がある新生児にも対応できるよう、新生児周辺のあらゆる診療科がそろっている。専門領域を持った50歳代のベテラン新生児科医も多く、一人の医師が診る新生児の数も多い。このように、研修医にとっては恵まれた環境であるにもかかわらず、これまでは地方からの多くの研修希望者に対し、公立病院の職員数の法律上の規定を理由に受け入れを断らざるを得なかった。豊島氏は「これを何とかしたかった。NICUの重症患者数は出生数に比例する。例えば、神奈川県での1か月の新生児医療の研修は、神奈川県の人口の5分の1の地方での研修の 5か月分に相当する。都市部のセンターで経験を積めば、地方に戻って活躍してもらえるようになるはず」と、提案を思い立った動機を語る。
同センターには、早産や出生前診断された重症の先天性の病気、外科手術が必要な病気の新生児が集まる。どんな重度の疾病や障害がある新生児にも対応できるよう、新生児周辺のあらゆる診療科がそろっている。専門領域を持った50歳代のベテラン新生児科医も多く、一人の医師が診る新生児の数も多い。このように、研修医にとっては恵まれた環境であるにもかかわらず、これまでは地方からの多くの研修希望者に対し、公立病院の職員数の法律上の規定を理由に受け入れを断らざるを得なかった。豊島氏は「これを何とかしたかった。NICUの重症患者数は出生数に比例する。例えば、神奈川県での1か月の新生児医療の研修は、神奈川県の人口の5分の1の地方での研修の 5か月分に相当する。都市部のセンターで経験を積めば、地方に戻って活躍してもらえるようになるはず」と、提案を思い立った動機を語る。
この研修では、中堅医師が既に勤務している現場を長期間離れなくてもいいように、個人の状況などに応じて3か月以上1年未満の研修を用意している。来年2月の県議会を経ての正式決定だが、4月に募集する3人の枠には既に7人ほどの問い合わせが来ている。「現場のニーズに合っていたのだと思う。特に、専門医不足が深刻な地方の病院からの問い合わせが多い。この研修が、地方病院からの退職を思いとどまってもらう動機付けになりそうだとも聞いている」(豊島氏)。
神奈川県は慢性的にNICUが不足しており、県外への母体搬送が2006年に100件、07年に70件あった。同センターにあるNICU の21床も常時ほぼ満床だ。「神奈川県は『新生児医療過疎』と感じる。NICUの需要に対して提供できるNICU病床が少なく、お産の時に新生児がNICUを必要とする状態に陥っても、迅速に収容し切れないこともある」(豊島氏)。県はNICU病床を増やす方向だが、専門性の高いNICUでの医療を実施できる新生児科医の育成や確保は、一朝一夕にできることではない。この短期研修医制度には,研修医を教育する代わりに、神奈川県の新生児医療を地方の中堅医師に助けてもらえるというメリットもある。
豊島氏は、「県がNICU病床を増やす方向であることはありがたい。しかし、働く新生児科医がいなければ、増床した病床を有効に使えない。増床には新生児科医の増員が不可欠で、新生児科医の育成が急務。新生児科医が少ないことを行政や政治家に対して訴えても、新生児科医を増やすことはできないだろう。現場の中で自分たちでできることを頑張り、新生児科医の育成に力を尽くすから、行政には教育へのサポートを求めたいと思った」としており、現場と行政との協同で医師養成を進めていく考えだ。
■「2人当直制」で若手の安心につなげる―埼玉県
埼玉県で唯一の総合周産期母子医療センターである、埼玉医科大総合医療センター総合周産期母子医療センター長の田村正徳氏は、「地方の場合は、その地域での医療を志す人の思いによって何とか保たれていることもあると思うが、病院が多い都市部でこのような過重労働では、辞めてほかに行ってしまう。若い医師には安心して入局してもらいたい」と、若手の安心確保が重要と指摘する。 人口約1300万人に対して9か所の総合周産期母子医療センターがある東京都と比べて、約714万人に1か所しか総合センターがない埼玉県の新生児医療の状況も深刻で、県内で生まれた重度の疾病や障害がある新生児の3割が都内に搬送されている。こうした厳しい状況の中、埼玉医科大総合医療センターでは02年から、小児科の当直を経験の浅い若手医師と指導医クラスの医師が一緒にできるよう、2人体制にした。「当直回数は倍になるが、若い医師が『一人は怖い』と感じる不安の解消につながった。忙しくても安心して現場にいられ、勉強にもなる」(田村氏)。当時、小児科医は15人だったが、今では倍以上の33人になり、このうち新生児科医も6人から13人にまで増えたという。
人口約1300万人に対して9か所の総合周産期母子医療センターがある東京都と比べて、約714万人に1か所しか総合センターがない埼玉県の新生児医療の状況も深刻で、県内で生まれた重度の疾病や障害がある新生児の3割が都内に搬送されている。こうした厳しい状況の中、埼玉医科大総合医療センターでは02年から、小児科の当直を経験の浅い若手医師と指導医クラスの医師が一緒にできるよう、2人体制にした。「当直回数は倍になるが、若い医師が『一人は怖い』と感じる不安の解消につながった。忙しくても安心して現場にいられ、勉強にもなる」(田村氏)。当時、小児科医は15人だったが、今では倍以上の33人になり、このうち新生児科医も6人から13人にまで増えたという。
田村氏は、「後期研修で小児科を志望する人は結構いる。彼らに十分必要な実習をしてもらうには、安心して当直できる体制をつくっていかなければいけない。それには行政のサポートも必要」と話す。
■国に現場改善のサポート求める 今年11月5日、東京都内で脳出血を起こした妊婦が8病院から受け入れを断られた後に死亡した問題を受けて、今後の周産期医療と救急医療の連携など対応策を検討するための厚生労働省の懇談会が開催された。
今年11月5日、東京都内で脳出血を起こした妊婦が8病院から受け入れを断られた後に死亡した問題を受けて、今後の周産期医療と救急医療の連携など対応策を検討するための厚生労働省の懇談会が開催された。
委員には産婦人科医や新生児科医、救急医や一般国民の代表が名を連ねた。委員として会合に出席した田村氏らは、新生児医療の現場を改善していくためとして、
▽交代制勤務を導入できるような支援
▽医師事務作業補助者の算定要件の緩和
▽看護師や助産師の補助業務拡大や役割分担の推進
▽後期研修医への奨学金導入への支援
▽NICU増床など施設整備に対する支援―などを求めた。
2か月弱しか議論の期間がないまま、報告書は近くまとまるが、行政はどこまでこうした現場の声に答えられるだろうか。
豊島氏は、「付け焼き刃的な政策の決定を望んでいるわけではなく、多くの国民にNICUの現状を知ってもらいながら、腰を据えて継続的にNICUの未来を一緒に考えてもらいたいと願っている。NICUの現場にいるわたしたちは、患者さんやご家族の声に耳を傾けて、子どもによりよい未来を届けるつもりで、今後ともあきらめずに頑張っていきたい」と力強く語る。
網塚氏ら現場の医療者が声を上げ始めたことにより、ようやく見え始めた新生児医療の実態。国民や行政は今後、どのように新生児医療にかかわっていくのだろうか。そして医療者自身は、現場をどう再構築していくのだろうか―。
未熟児の親の“声”
医療者側から見えてきた新生児医療の実態。では、NICUに入る赤ちゃんたちの両親は何を感じているのだろうか。インタビューに応じてくれた3人は、「生まれた子どもがNICUに入院した」という共通点はあるものの、生活や周囲の人間関係がまるで違うため、語る内容は全く異なる。しかし、そこから見えるのは、それぞれが医療者への感謝の念を持ちながらも、同時に不安や疑問も感じていたということ。そして、そのためにフラストレーションを抱えていたということだった。親が語る“声”を聞いた。
■「今なら先生の気持ちが分かる」
京都府近郊に住む主婦の田中弥生さん(仮名、30)。今から5年前に結婚し、すぐに子どもができた。妊娠の経過は順調で、何の問題もないと思われた。しかし妊娠24週に入ったある晩、いつもよりおなかの張りを感じた。特に心配はしなかったが、翌日に出血が2度ほどあったため、気になってかかりつけの産婦人科医に電話した。「『大丈夫だと思うけど、一応来てみる?』と言われて行ってみた。そしたら、子宮口がかなり開いていたので、先生が急いで大きい病院を探してくれた」。
入院してからは、早産にならないようにするためにさまざまな処置が施されたが、3日目に子宮口が完全に開いた。「夫は担当の先生から、子どもが助かるか助からないかは五分五分で、何らかの障害が9割の確率で出ると言われていた。わたしはその先生から、帝王切開の方が母親への負担が大きいといって自然分娩を薦められたので、それで頑張ろうと思った」。田中さんは自然分娩で出産し、生まれた赤ちゃんは約580グラムの未熟児。すぐに保育器に入った。
その後、田中さんの子どもは大きく成長し、今年で3歳になった。ただ、水頭症など重度の障害を残し、現在は肢体不自由児通園施設に通っている。田中さんは、「今でも、これでよかったのかなと思うことがある。もし、帝王切開にする方が子どもへの負担が小さいとその時に聞いていたら、そうしたかもしれない。そうしたら、今の子どもの障害の状態が違っていたのかもしれないと思ったりする」と、整理し切れない当時の気持ちを語る。 「子どもの手術を勧められても、わたしたちには医療のことは分からないから、その手術が本当に適切なのか、どんな手術なのか、インターネットで調べるぐらいしかできない。子どもがそこに入院しているからセカンドオピニオンなんて取れないし、とにかく子どものことで頭がいっぱいで、不安だった。でも、看護師さんやお医者さんは本当によくしてくれたので感謝している。看護師さんは不安を聞いてくれたし、症状のことだったらすぐに先生が対応してくれた。でも、やっぱりそれでも不安だった」
「子どもの手術を勧められても、わたしたちには医療のことは分からないから、その手術が本当に適切なのか、どんな手術なのか、インターネットで調べるぐらいしかできない。子どもがそこに入院しているからセカンドオピニオンなんて取れないし、とにかく子どものことで頭がいっぱいで、不安だった。でも、看護師さんやお医者さんは本当によくしてくれたので感謝している。看護師さんは不安を聞いてくれたし、症状のことだったらすぐに先生が対応してくれた。でも、やっぱりそれでも不安だった」
それでも、最近は穏やかな気持ちで生活できていると田中さんは話す。子どもと生活しながら感じる最近の気持ちについて、「今は平和で幸せだと思う。今なら、先生が一生懸命助けよう、よくしてあげようとしてくれていた気持ちが分かる。不安も不満も感じたけど、わたしはよくしてもらえた方だと思う。生きてれば、幸せな瞬間はやってくるんだと思う」と、明るい声で語った。
■「助からない方が…」
「自分や子どものことで頭がいっぱいで、医療側のことを考える余裕なんてなかった」と話すのは、東京都内に住む赤石恵理子さん(仮名、33)。
赤石さんは、妊娠25週の早産だった。田中さんと同様、出血から不安を感じ、かかりつけ医が連絡して都内の周産期母子医療センターに搬送された。「苦しかった。とにかく苦しくて、お医者さんだけが頼りだった」。生まれた赤ちゃんは約570グラムの未熟児。赤石さんは1週間ほど入院して退院した。しばらくは毎日NICUに通ったが、そのうち足が遠のいてきたと話す。「NICUにはたくさんのお母さんやお父さんが来て、赤ちゃんを抱っこしたり、ミルクを飲ませたりしている。それを見ていると、気持ちがぐちゃぐちゃのまま、何でも話し合える相手がいない自分がどうしようもなく悲しかった。赤ちゃんもこれから障害を持つのかと思うと、かわいそうになった。小さい彼と目が合うと気持ちを見透かされているようで、来づらくなってしまった」。赤石さんは、シングルマザーだ。
赤ちゃんがNICUにいたころに、受け入れ先となる施設を探したが、なかなか決まらず、NICUに1年近く入院していた。「最後の手段」(赤石さん)として、両親に事情を話して実家に戻ることを決め、仕事を辞めて子どもの世話をしながら生活することにした。今、子どもは2歳になろうとしている。「最初は実家での生活は考えられなかった。子どももわたしも元気なら、保育所に預けて何とか生活できると思っていたけど、子どもは常に世話が必要になってしまった。最初は一人暮らしのまま何とかできないかと思ったけど、施設は見つからなかったし、一人暮らしだと仕事を辞めないといけなくなる。そうすると収入がなくなって生活できなくなり、生活保護になるのかと考えたりして、目の前が真っ暗になった」。赤石さんが実家の両親と、子どもや今後の生活などについて話し合うことは一切ないという。
赤石さんは、「子どもが助からない方がよかったのかもしれないと思うことがある」と語り、涙をこぼした。
「昔だったら医療がこんなに発達していないから、小さい赤ちゃんは助からなかったと聞く。じゃあ、わたしの子どもも昔なら助からなかったのだろうか。この子はわたしみたいな親の元で障害を持って生まれてしまい、かわいそう。子どもが生まれた時に、お医者さんも看護師さんも『助かってよかったね』と笑顔で言ってくれた。NICUでは、看護師さんはわたしが来ると寄って来て、状態を聞かせてくれたし、お医者さんも話を聞いてくれて、本当によくしてもらったと感謝している。あんなにも一生懸命に頑張ってくれている人たちに『助からない方がよかったのかも』なんて、口が裂けても言えない。言ってはいけないと分かっている。でも、そういう一番不安な気持ちを話すことができなかったから、ずっと安心し切れなかった」
■「2種類の国民にどう対処する」
未熟児の子どもを亡くした経験のある、東京都内に住む北野達也さん(仮名、32)は、「最初、NICUでこれだけの医療を受けながら、自分たちが払っている医療費はおむつ代の数百円というのがおかしいと思った」と話す。自身の経験を通して、さまざまな本を読んだりして情報収集し、社会的な問題として新生児医療について考えるようになったという。
「10年前なら亡くなっていたような子どもが助かるようになった。自分としても、翌日に亡くなっていたかもしれない子どもと、半年間一緒にいられたことに対しては感謝している。ただ、社会全体の中で限られている資源の配分をどうするか。『ここからはできない』という線を引かなければいけない。どこまではできて、どこからはできないのか。医療者から提示していかなければ、国民には分からない」
北野さんの子どもが手術を受ける前に、医師から話を聞く機会があった。北野さんは、「自分たちは手術以外にどういう選択肢が有り得て、その中でその手術がもっとも適切である理由はどういうもので、手術にかかわるリスクにはどのようなものがあるか、ということを聞きたいと思っていた」と言う。しかし、医師が話したのは、「メスをどこから入れるか」という技術的なことで、自分たちが欲しいと思っていた情報とはまるで違っていた。北野さんは、「医学の正確な知識を理解したいと思っても、医師の言語は分かりにくい。医師側から国民に分かりやすい情報は流れていないので、ネットなどで情報を収集するが、そこには医療に対して怒りを持った人が発信している情報もある。自分の置かれた状況や事情と、そうやって得た情報が合わないほど、医師に対して不信を持つようになる」と語る。
また、「患者にとっては家族の問題などは大きいけど、医師にとってはどうでもいいもの。だけどそれが患者にとっては大問題だから、医師と患者の話は合わないと思う」と話す。
北野さんは一般国民と医療者のこれからの関係性について、「国民側には、自分が深刻な経験を抱えているために医療に対して求めるものが多い人、そして全く何も考えていない無関心な人の2種類がいる。これに医療側がどう対処していくかがこれからの課題では」と語った。
語る言葉はまるで違うが、医療や医療者に対してそれぞれ整理し切れない思いを抱え、「感謝」と「不安」が交錯する患者の心。北野さんは、「ネットには患者も情報を載せているが、声を上げていない人の方が圧倒的に多い」と話す。声となって聞こえてこない患者の声。一般国民と医療者はどのようにかかわり合いながら、今後の新生児医療を形づくっていくのだろうか―。
コメント